魔界の海を泳ぎ、プエルラはわずかな力を振り絞り島へと向かった。
無我夢中で体を動かし、やがて目の前に浅瀬が現れ、小さな手が浮力から離れた瞬間_
プエルラは海の藻屑と共に、力なく波に晒され全身を脱力させた。
しばらく倒れていると、プエルラは胸や腕、腹の傷口を撫でるように触れた。
そこには、痛みがなくただ、皮膚が開いているであろうという凹凸の感覚しかなかった。
否、無くなっていた。
プエルラはその場から起き上がり自身の体を見た。
すると、凹凸を感じていた傷口の箇所がすべて深く、黒く染まっていた。
黒と、白に染められた肉体にプエルラは過去の姿を照らし合わせる。
他者から見れば、今の自分は醜く変貌していく異常な傷を持った哀れな少女に過ぎぬ。
プエルラは、自身の身に着けていたマントを引き裂き、胴と腕に巻きつけると立ち上がり、島の奥へと進んでいった。
「だめだ、見つかりません」
城のエントランスにて、捜索隊の悪魔がユンガに報告する。
ユンガは報告を聞くと、下を向き俯いた。
「ユンガ様……もうかれこれ三週間も続けざまに探しているではありませんか……しばしおやすみになられては如何かと」
捜索隊の一員のリザードマンが飛び出し、眉をひそませユンガに言った。
そういうのも無理は無かった。
ユンガの顔には隈が色濃く浮き出ていたのだ。
「大丈夫……そんなことより、別の捜索隊は……」
ユンガは姉が失踪してから、ありとあらゆる手を尽くし姉を捜し出すことに躍起になっていた。
それもその筈、姉にはある特異な”病”にかかっている可能性がある事を病院内の大悪魔たちにしらされていた。
病の名は、莫大な魔力を有する魔族がかかり易いという、【反転浸食病】。
かつては原初の魔族しか発症しないと言われており、自身の身に宿る属性と相反した属性を宿したものに瀕死に至るほどの致命傷を負わされる事によって、まれに発症する病。
その病にかかれば、まず臓器をむしばまれた後角や頭髪といった身体の一部の変色などが特徴として見られるという。
そして、最大の特徴_それは、性格の豹変と魔力の弱体化、精神への負荷である。
それは自身の有する属性と交わるはずの無い対極の属性が、宿した魔力によって体内で浸食に抗い、でたらめに中和されることによって起こる免疫現象。
それにより、個体差はあれど精神が不安定な状態になり魔力を使用し魔術を練り上げ放出させることが難しくなり、さらに属性が魔術を使う際に体内で相殺されるため単純な魔術の質が下がることとなる。
これらの症状に加え、この病は発症すれば二度と治療が不可能な上、魔術を使えば使うほどに精神に負荷をかける為寿命を縮ませるという。
治療が不可能とされているのは、発症者の体を永遠に相反する属性が浸食し続ける性質から、魔力の籠められた装飾品により浸食を抑える事はできれど一度注入された属性を取り出すこともできないからである。
浸食が進めば最悪の場合_適合できずに肉体が崩壊する。
ユンガは、発病の条件がそろっていながらも失踪した姉を不眠で探し回っていたのだ。
「全精力を以て、姉上を捜し出せ!! まだ絶対生きてるはずなんだ!!……けほっ……げほっ……」
細身の体から、必死に声を絞り出し帰還した捜索隊に指令を下す。
気迫にあふれた声は、城中に響き渡りこだました。
声が変わる前にも関わらず、そのユンガの声には確かに”テネブリス家”の魂が宿っていた。
捜索隊の魔族は、翼を広げ玄関から飛び出していった。
その数、総勢約二五〇体。
ユンガは捜索隊の出発を見届けた後、その場でうつむき、ぽつりと零した。
「……お願いだから」
誰も居ないその城は、小さな声も包み込んだ。
「ユンガ・テネブリスよ!」
ユンガの名を呼ぶ声が、城の天井から聞こえてきた。
ユンガがその場から上を見上げるとそこには、巨大な翼を広げた獣の影があった。
その影は紛れもない、魔獣属の王_ダークキマイラである。
砂埃を巻きたてながらキマイラはユンガの目の前で着地し、獣の姿から人型の姿へと変化させた。
「き……キマイラ様!?」
「様呼びは止さぬか、ユンガ」
ユンガの頭を撫で、その場でしゃがみ込みキマイラは微笑んだ。
「お前……無理はしておらぬか?」
口に出たのは鋭い瞳の獣らしからぬ、意外な一言だった。
「いえ……これでも偉大な現魔王の端くれですから……」
ユンガが目を合わさずに答えると、キマイラは表情を変え語った。
「……ふっ……現魔王か、歴代悪魔属の王の中では腑抜けだったのう」
口元を、鋭くさせながらの言葉。
それにユンガは感情のままに、目の前の魔獣属の王の顔に拳で返した。
「っ……?」
「それは、僕たちへの侮辱か……? 魔王さま……!!?」
キマイラにとっては、何も痛みを感じない、それでも重い一撃だった。
キマイラはどこか期待通りといった表情を見せ、続けた。
「そもそも……お前たちの一族は皆から反感を買っておるようだぞ……? ”ダーク”と名がついてもいないにも関わらず魔王の座に座るなどおこがましいとな」
「それだけではない、お前たちは魔族として異常なのだよ……魔族は基本原初に生まれた存在の血が濃ければ濃い程魔力が強い傾向にある……」
「今回の件で、テネブリスの一族が全滅して清々したという者が多くいるぞ……? やはり、弱小魔族に過ぎなかったようだなと」
ユンガは、キマイラの挑発的な言葉の数々を黙って聞いた後、震える拳をキマイラの顔面に力いっぱい叩きつけた。
勿論、効くはずも無い。
しばらく何度も拳を受け続け、キマイラは突然立ち上がった。
「……良い!!」
大声で何かを確信した様子で言ったのち、ユンガの腕を持ち上げた。
「!?」
ユンガは、突然ふわりと体が宙に浮いた感覚にさらされた。
状況を飲み込む間もなく、ユンガはキマイラに持ち上げられ気が付くと腕に抱きかかえられていた。
「……なんですか」
しかし、反抗は崩さずに顔を歪めた。
「ユンガよ……我々と組まぬか?」
眼を輝かせながら放たれた提案だった。
「……ふぇ?」
提案と、先ほどの侮辱の様子とのギャップからユンガはさらに戸惑った様子で首を傾げた。
「えと……どういうことです?」
「実は、魔王達の間で……人間を滅ぼさないかという話があがってな、ベリアルにルシファーと我、そしてダークリザードマンで同盟を結んだのだ」
キマイラは、嬉々とした様子で語っていた。
「本来ならば現魔王たるお前の父にも協力を仰ぎたかったのだが……その血を継いでいるお前がもし、我に攻撃できる程の器の持ち主であれば加入させようとしておったのだ……」
キマイラの目が、ユンガの顔をじっと覗く。
すると、ユンガはキマイラに強く言った。
「……申し訳ありませんが、お断りします」
「!?何故だ!?」
眼と口を大きく広げ、キマイラはユンガを抱えた腕を離した。
「……まず、僕はただ単に家族がすごいだけの何のとりえもない一匹の悪魔に過ぎません。だから、恥の無いようにふるまっているだけなのです」
「それに、魔王の方々にとっては知りませんが僕にとっては戦より今は姉上を捜し出さなければいけません」
「今はたった一人の……家族だから」
出たのは淡々とした語り口だった。
しばらくの硬直ののち、キマイラは声高らかに笑った。
「あっはっはっは!! 良いぞ! それでこそユンガだ!! ますますお前は我を魅せてくれる!!」
「良いだろう、我もしばし協力しよう……」
ユンガは、乾いていた瞳を潤わせた。
「ありがとうございます……!!」
心からの、言葉だった。
それを聞いてキマイラは笑顔で返し、後ろを回り咆哮した。
キマイラが地響きを立てるほどの凄まじい咆哮をすると、一分もかからぬ内に様々な姿形をした魔獣が城に集まった。
「キマイラサマ、メイレイ……」
ゴリラに似た姿をした魔獣がその場にひざまずくと、一斉に魔獣の軍団が平伏した。
「良いか!! 我の気に入った者の姉を探せ!! こいつに似た美形の顔たちをした少女だ!!よく見ておけ!!」
命令を聞くと、魔獣たちは各々鳴き声を上げた。
そして、キマイラはユンガの方を振り向いた。
「ふむ……では、ユンガよ。念には念をだ、姉のよく使っていた品は無いか?」
「使っていた品?」
「ああ、悪魔は知らないかもしれないが、魔獣は嗅覚が優れていてな。それ故、獲物を索敵するのに長けているのだ」
それを聞き、ユンガはポケットから焼けて血がこびりついた布の切れ端を渡した。
「姉さまの法衣の切れ端……これでもよければ……」
そういった瞬間、キマイラは差し出された切れ端を嗅いだ。
「……これでは、血が焼けていて流石に嗅ぎ分け辛いな。なにか、もっとないのか」
そう言われ、ユンガは何かを思い出したかのようにすぐさま魔法陣を展開し、移動した。
しばらくすると、ユンガは再び何かを手に持った様子でキマイラの前に姿を現した。
それは、一冊の本だった。
「これ……ですか」
「これは……魔術書……しかも高等魔法ばかりの本ではないか」
「ええ、姉上はよくこれを祖父に渡しては……危険だからってしまわれていましたから」
「でもこっそり持ち出して、読めた気になって遊んでいたんです……」
ユンガは声を暗くさせながら、無理やりにでも声の調子をあげ語った。
「……すんすん……うむ……こんな匂い……なるほど、どこかお前に似ているな」
納得した様子で、キマイラは本を受け取り側近と思しきこうもり型の魔獣の口に咥えさせた。
咥えさせた後、キマイラは本来の姿となり翼を広げた。
「……ぼくも行きます」
ユンガがキマイラに近づくと、キマイラは尻尾でユンガの顎を撫でた。
「こればっかりはだめだ、お前が居ずして誰がこの城を守るのだ?」
「それに、お前は少々身の丈に合わぬ苦労をしすぎだ、しばし休め」
後ろを向くことなく、キマイラは魔獣の軍団と共にその場を去って行った。
ユンガは、本を握っていた自分の右手を見て、呆然と立ち尽くしていた。
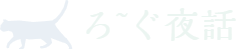


コメント