何者をも通さぬ、狭く暗い洞窟に少女はたたずむ。
ピチョン、ピチョンと水の滴る海底洞窟にただ独り。
「はあ…っ!! 」
全身に力を籠め、魔力を回す。
目の前ですべてを奪っていった憎き男の顔を思い浮かべ、目の前に投影させ、標的として。
魔力を体から放出させて、念じてから数分程経過し、やっと少女の周囲に魔法陣が現れた。
しかし、現れた魔法陣のほとんどが少女の思っていた方向とは全く違う、でたらめな方向に展開されていた。
洞窟の床に数十個展開させるつもりが、壁や、天井に二つ一つとバラバラでかつ想定外の場所にばかり出現させていたのだ。
嘘だ、前はできていたはずなのにと焦燥感に駆られたように、上げた片手を震わせる。
再び念じ、片手を握り魔法陣から様々な形の武器を召喚させた。
現れた武具の全ては、白く濁った光を放っていた。
それらを発射させると、全弾が少女の体に突き刺さっていった。
「うあああっ!? 」
今まで経験したことのない、予想外の痛みだった。
痛みを感じることは何も、少女にとってこれが初めてではない。
それでも、よもや自身の魔術によって己の身を傷つけることになろうとは夢にも思っていなかったのだ。
それも、光に侵食された武器によって。
「っ…!! こんなはずでは…!! 」
剣、短剣、杖、斧の刺さった体を引きずり、再び魔術を使う。
次こそは、以前の様に扱ってみせると決意を抱き少女は力を籠める。
だが、いくら魔力を籠めようと全身が痛むばかりでいよいよ魔法陣すら現れなくなった。
少女の身に宿る魔力が底つきたのだ。
体に宿る魔力の量は生物によって異なり、魔術を使えば使うほどにその魔術の精度、魔力の量、容量が増えていく。
少女__プエルラ・テネブリスは無尽蔵の魔力を生まれつき持っていた。
その魔力が、いまや凡夫のそれと化してしまったという現実を惜しみ、少女は悔しさと屈辱に拳をうち震わせる。
震わせたその拳を思いきり地に叩きつけ、力、家族、全てを蹂躙し破壊していったあの男への憎悪を瞳に燃やし何度も地面を穿つ。
自身の拳が、紅に染められるまで。
「なんで………なんでなんだよぉっ!!」
少女の打ち付けられた憎しみと悲しみに染められた洞窟に声がこだました。
叫びを慰めるぬくもりも、届くことも無くただただ少女は何度も、何度も拳を紅く染める。
拳から流れる血すらも枯れはて、少女は拳を上げ激痛を堪えながらまた魔術を展開させた。
眠ることも忘れ、傷ついた体を癒すことも無く少女は召喚魔法を再現させることに努めた。
樹皮の剥がれた枯れ枝の様に細く白い腕から、灰色の魔法陣を生み出し、そこから姿を現す武器をを遠くに打ち出す。
単純で、誰にでもできる魔術。
それ以外の魔術を行おうとすれば、全身に激痛が走り更に光の浸食が進行する。
過去であれば、やろうと思えばいつでもできたはずの魔術でさえ発動が難しくなっているのだ。
しかしそうやってどれほど過去の力を惜しもうとも、現状が覆ることは無い。
故に、今できる全力を以てがむしゃらに鍛錬をする他に少女に道は無かった。
精神も、身体も、魔力もすり減らし洞穴にただ独り。
自分などとっくのとうに家族と共に死に絶えた。
今ここに在る我が身は、さながら意思だけを残した抜け殻だと少女は自虐的に悟る。
だったとしても成さなければならない目的、討たねばならない目”敵”がのうのうと大地を踏みしめ生きている。
力を蓄えたのならば、例え自身が滅びることになろうとも男に絶望を送り、あの瞬間に見せた愉悦の嘲笑を踏みにじってくれる。
人界で勝利に酔いしれ笑うのが貴様なら、魔界で嗤うがこの私______否
”余”なのだと。
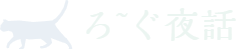


コメント