『怖かった』
『魔界の全てが蹂躙されていくあの光景が。
見知った連中の体が血しぶきをあげ、遺言に聞こえてくるのは叫び声。
止せばいいのにとでも言わんばかりの鮮血に濡れた顔は、憎らしくも歪むことは無い。
ただ冷徹なまでに、魔族を葬るその様。
私にできることはなかった。
飛び交う炎、雷、落石に嵐津波の魔術達。
身を貫くだろう吹雪の冷たさも、全てを覆い引き裂く闇すらも、奴はただ嗤い、悉くを受けて絶望を与える。
あの王の再来とさえ思った。
かの、魔王の器達を葬り、魔界の魔族を無差別に破滅させていった歴史の再現を目の当たりにしている。
そう思わせるほどに暴力的で、非情。
暴君と評されるあのバエル、破滅の王と呼ばれたアバドン、堕落の魔王とよばれたアマイモン。
そして――色香の王、アスモダイさえも。
アバドンの体を構成する全てを喰らう蝗害の嵐、アスモダイの幻惑魔術、アマイモンの圧縮魔術。
バエルの、あの全てを葬り去る牙も、奴の前では児戯に過ぎなかった。
アバドンの体の半分を喰らい、アスモダイの幻惑を破り、アマイモンの魔術を跳ね除けて。
バエルを、完膚なきまでに、打撃の五月雨で以て打ちのめす。
周囲を包み込む魔界の民の阿鼻叫喚。
それを、切り裂くかのように現れた者がいた。
絶望を照らす、明けの明星。
完全なる、初代魔王と呼ばれた者の放つ、炎と氷の魔術。
それらは奴の身を何度も焦がし、凍結させていった。
天界での決戦で、最終奥義として使ったという魔術を放ち、とどめかに思われた時。
奴の姿がそこにはあった。
消耗し、摩耗しきり、疲弊に打ちひしがれていたルシファーは――奴に何も抵抗を示す事無く呑まれていった。
私は、その姿を見て立ち向かわざるを得ず。
全魔力を展開し――たその刹那、奴は消えた。
余りにも、無力だった。
膝から崩れ落ち、地に両手をついた時聞こえてきたのは民の怒り。
憎みもした。
その怒りを持っていながら、何故貴様らは見ているばかりで戦おうともしない! と。
――が、同時にすり替えられた憤怒と憎悪の理由は、私が恐らく一番理解していた。
私が、魔界の上空で留まらず、最初から立ち向かって居ればこんなことにはなりはしなかったのだ。
故に、あの魔族らと私は、そういった意味でも――同罪。
であるとするなら、誰にも文句は言えなかった。
私は――』
「何書いてるの?」
青年の背後から、少女の声が響く。
青年が手にした本を万年筆を挟み閉じて振り返ると、愛魅が顔を覗かせているのが見えた。
青年は笑み、愛魅の顔を撫でる。
「いつもの、小説だよ。ちょっとした小説」
愛魅が青年の肩に身を預けると、愛魅は一呼吸した。
「ねぇ、“ロー”、良かったの? あいつ逃しても」
愛魅が問うと、ローが答える。
「……大丈夫、あいつらは放っておけばすぐに死ぬ。片腕を無くした少年に、強大な相方……互いのパワーバランスが偏っているのなら、自壊は近いだろう」
ローが言った瞬間。
どこからともなく声が聞こえてきた。
教会の扉から、後光とともに。
「そうだとも、パワーバランスは大事だ……例えば、こんな風にな」
凛とした、女性の声が響くと同時に――銃声の数々が、静寂を破った。
外界から射す光を反射した、散らばっていく美麗なステンドグラスにも惜しげなく弾丸を浴びせかけていく。
「撃てェ!! 肉片一つ残すなァ!!」
女性の声と共に、横隊列の兵士達が小銃に込められた弾倉の中身全てを放つ。
一方的な弾丸の射程はまさしく剣の刺突に等しく。
弾幕で視界が包まれた時。
「……ハガード隊長、これであの寛大聖教の教会は……」
隊の中の一人が、隊列の中央で構える女性に言うと、女性――麓・ハガードは煙管を咥えつつ答える。
中身に、ライターで火を灯して。
「間違いなく、これで魚渡区の教会は全滅。銀髪の怪物の反応が消えたのなら、後は怪異の残党どもをこうして殲滅するだけで済むんだから、楽になったものだ。……あの少年には、そういう意味でも感謝したいわね」
全隊が、安堵を許した直後。
一筋の、光輝が三人の兵士の首、頭部を貫き、あるいは切り裂いた。
恐ろしいまでに清廉なる教会の、絨毯に包まれた床が紅に染まると、麓はすぐ正面を向く。
すると、破られたステンドグラスから見える外の景色が、ぼやけていることに気付いた。
「グ、手榴弾!!」
麓が正面で剣を構える愛魅を前に、腰に付けた、手榴弾の先端のピンを外し――。
投擲する。
爆発と硝煙に包まれた教会内は、全くの無傷。
少女は、笑みをたたえるばかりで何も動じていなかった。
「そんなバカな話があったとは……」
麓は小銃を構え、愛魅を狙い撃とうとすると、背後から巨大なものが落下するかのような音が響く。
音につられるまま、後ろを向くと――そこにはおぞましき造詣の怪物がたたずんでいた。
猛禽の翼の下には、コウモリの羽が生え、顔は山羊に似て鱗の様に光る粘液の髪に覆われており、瞳孔は十字を模したが如く。
体は、灰色のジャガーを彷彿とさせ、尻尾はカギのようになっている。
教会の天井に窮屈げに背中を擦り付けるそれは“雑種”と呼ぶにふさわしい、が――故に、未知としての恐怖を麓に与えてならなかった。
「ばかな……こんなやつは、みたことない……!!」
麓の足元が震えると、鮮血に濡れる少女、愛魅がゆっくりと雑種の側に寄る。
「ロー、ちょっとビビらせすぎじゃない?」
愛魅が近づくと、ローは頭を垂れ、体に向かって頬ずりのような仕草を見せた。
「お……お前! 寛大聖教の教えに背いている筈じゃあないか!? ましてや祓魔師が、主以外の魔族を……そんなに愛でるなど!」
麓がローに向かい、軍服のポケットに入れていた回転式拳銃を向けると、引き金を引く。
放たれた弾丸、それは銀色だった。
「銀の弾丸は、お前たち魔族の弱点じゃなかったか、くたばりなさい!」
麓が何度も引き金を引き、発砲する。
が、ただ愛魅もローもその様子を嘲笑うかのように――口許を歪ませていた。
「もういいや」
愛魅がそう言った瞬間、麓の胸に剣が押し込められる。
剣から伝わる、脈動ごと――麓を否定するかのように。
「そうだね、パワーバランスは大事。……ローが守って、私が、とどめを刺す。……お前の場合は、ただ部下を総動員させて火力をでたらめに出しているにすぎないんじゃない?」
「……それに、教会の全員にばれていなければ、いいじゃない」
愛魅の剣が、引き抜かれる刹那――青年の声が、麓の耳元で聞こえてくる。
「そんなに、お前達は自分ら以外の存在を認めたくなかったのか……再会することがあったら、また会って語らおう……冥界か、天界かは知ったことではないけど」
冷たく言い放つ、その声。
冥土の土産になったかは、もはや誰の知る由もなかった――。
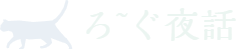


コメント