開けられた扉の前に広がる、風景。
それは、軍事基地を彷彿とさせる空間だった。
巨大な建物の前の両脇には、攻撃ヘリが横二機ずつ一列に並んでおり、ヘリの後ろでは無数の装甲車が駐車されている。
ヘリには、青と灰色の迷彩が施され翼の様にガトリングとミサイルが積まれており、広大なヘリポート内に所狭しと鎮座していた。
ヘリ達に挟まれた、白タイルの道を麓が歩きだす。
麓は、車の扉から数歩歩いたところで、後ろを振り向き、首を前にやった。
すると、Fencer隊員が一行を車から出る様に促し、快らを車から降ろしていく。
手に持ち、匂わせている、緊迫感をそのままに。
白光りする道を、一行は歩いていった。
「おいおい、あそこを見てみろ皆」
棕が指さした先は、建物の奥。
白い、軍事基地を思わせるそこの奥に構えていたのは、巨大な壁だった。
(大きな壁…………いったい何メートルなんだろ)
快は、遠方から見える、基地の奥にそびえたった壁を見上げる。
上に注意を向き続ける首を痛めながら、歩んでいると麓の声によって、真正面に視点は戻されていった。
巨大な壁と、白塗りの建物以上に――快にとってその発言は、注意を引き付けるのに相応しいものであった。
「ここは、天護県天護町の最北端――すなわち、君らの見知った世界と、未知の世界との境界線上にある場所だ」
天護県は、たった一つの広大な町がある県として扱われており、北陸地方の北に位置する。
それは、快も、棕も知っていた。
しかし、その最北端に壁が築き上げられているということは、知らない。
大規模な建造物と、土地の境界を示すような重要な場所であれば、何らかの媒体で知らされるものであるが――世界を知る棕でさえ、天護町を知りつくした快でさえも知らずにいた。
一行が麓に導かれるまま歩いていくと、建物の自動ドアが開かれる。
自動ドアの先には、病院の受付を彷彿とさせる窓口があり、その手前に白い四角柱が来訪者を挟み込むように置かれていた。
麓が四角柱の上に――身に着けていた小銃、拳銃、手榴弾を置くと両腕を広げる。
すると、四角柱からは赤い光が差し込み、それは麓の頭頂部から足首までに向かって伸びていった。
赤い光が二往復し終え、四角柱は役目を終えたように光を閉ざしていく。
四角柱の上に乗せた、装備品を回収すると、麓は後ろを向き一向に言う。
「君らも、金属物があれば四角柱の上に置いて検査を受けなさい。これは赤外線によって、危険物を判定するの」
麓の発言に、快は苦笑を浮かべざるを得なかった。
快の後ろで、その様子を見ていたグリードが、快の肩に手を置いて――悪戯な笑みを浮かべる。
「体の半分くらいが金属だったら、どう反応するんだろうなぁ? 楽しみだ」
グリードの声に、真面目に麓が返答した。
「金属に反応すれば、すぐさま訓練室以外の部屋が封鎖。三つ数えぬうちに警報が鳴ると基地で訓練中の実働部隊がやってくるわ」
麓の声は、快の脳内の、申し訳程度の楽観を無慈悲にも打ち砕く。
「あの、金属でできた義手義足って――」
快の不安げに発せられる言葉を遮り、グリードが背中をつついた。
「早くしてくれ、つっかえてるんだぞー?」
驚きの声と同時に、快の足がもたつき身構える前に快の体は四角柱の中に自然と放りこまれていく。
四角柱からは、機械的に赤い光が放たれ、快の体に照射されていった。
グリード以外の全員が、一体となって頬に滝のような汗が流れていく。
それは快が一番感じ取っている事だった。
(何やってるんだよグリード! 恨むからなぁぁ!?)
しかし、叫びとは裏腹に光は、麓と同様に二往復した後何事もなかったかのように光は四角柱の中に吸い込まれていった。
「あれ、なんともない」
快は自身の右腕や足回りを撫でる。
入り口付近に溜まっている、棕とグリードの背後にいる隊員もその様を見て胸を撫でおろしていた。
「面白くなりそうだったのに」
「とんだ茶番に付き合わされそうだったわね」
そこには、笑みをたたえる麓の姿があった――。
入口を右に回り、一行が長い廊下を進んでいくとサンドバッグやランニングマシンなどの器具が置かれた広い部屋が両脇から覗かせていった。
部屋の中は、汗の臭いで充満していて蒸し暑く、湿った空気感が通った者の肌を伝わせる。
部屋を通過した先には、白い、番号のつけられた扉が左右にいくつも連なった空間に辿りつく。
「ここは、Fencer隊員の待機室。いつでも命令一つで出動できるよう中は必要最低限の広さしかないのだけど――実質的な生活空間にしてる隊員も多いわ、タケル、シンヤ、あなたたちもそうしてるんでしょう」
先に立っていた麓が振り向き、一行の後ろについているFencer隊員に目を向けながら言う。
声をかけられたFencer隊員が頭を撫でて反応を返すと、麓は眉を一瞬ひそめ、ため息をつくと再び廊下を進みだした。
延々と続くと思われた白い廊下と扉の連続に、快が欠伸を漏らしていると、棕が肩をつつく。
後ろを向くと、棕の指が快の頬に食い込んだ。
反応を示したのをいい機会とばかりに、小声で棕は快に話しかける。
「なぁ、いつになったらうちらは解放されるんだろうな」
棕の小声に気付いた麓が、快の代わりに歩みを止め、答えた。
「この廊下の最奥にあるものを、見せてからだ。まずは、そこで話そう」
快と棕、グリードが麓の後ろの正面を見ると、そこには巨大な金属製の扉が構えていた。
巨大な扉には、赤いボタンがついており、麓がボタンを殴るように押すと――扉から警報が流れる。
けたたましい警報が響き渡ると、一行の背後はシャッターが次々としまり、封鎖されていく。
『Warning plese don’tmove it was not plactis. warning plese don’t move it was not plactis』
機械音声が、静止を促す。
それと同時に、徐々に巨大な扉は開かれていく――。
巨大な両開きの扉の中が露わになると、そこには――――動物園を彷彿とさせるガラス張りの部屋が複数存在していた。
「ここが、Fencerの研究室よ。ここでは、様々な魔術、太古の遺物関連の研究物がごまんとある。もちろん、その多くは――“禁忌属”への対策に使われているけれど」
一行から見て右側のガラス張りの部屋は、番号が割り振られており、様々なものが入れられている。
手前の部屋は、本棚になっており、快がガラスに張り付いてみたところでは、本の一つ一つが薄いビニールに覆われているようだった。
快が本棚の部屋を見終えると、今度はその隣の部屋にはりつく。
しかし――その部屋は明らかに他の部屋とは一線を隔すような異様な空気感を醸し出していた。
二本の剣が剣立てに置かれており、常に帯電している。
それだけでなく、その剣を支える剣立て自体が、その剣を拒むかのように震えていたのだ。
だが、それ以上に、快の心はどこか、その双剣の美しさに心惹かれていた。
幻想的に煌めく、翡翠を極限まで磨き上げたが如き、稲妻をからめとった刀身。
老若男女問わず、その剣の造形に魅了されるのはもはや必然的であった。
「その剣が、件の禁忌属に対する最終兵器よ」
剣を眺めていた快に、しゃがみこんでいた麓の声が耳元でかかる。
「正確に言えば、まだ試験段階なのだけどね」
「麓さん、なんでこうして本だとかがガラス張りの部屋に閉じ込められてるんですか?」
快の質問に、麓は返した。
「“禁忌属”について書かれた文献は貴重なの、情報の書かれた大昔の写本にさえ、抽象的な事しか書かれていない。だからああしてまとめておくと同時に籠められた魔力の暴発を防いでいるの、魔術書かもしれないし。そして、あの剣はやっと入手した伝説の金属を加工し、英雄の使っていた剣を元にして作ったものなの」
麓がそう話していると、後ろから白衣を着た男がやってくる。
白衣の男に、麓は握りしめていた袋を渡すと、白衣を着た男は無言で頷き、奥の扉へ入って行った。
入って行った扉に書かれた看板には、“禁忌生物研究部門”と書かれていた。
「さて、この生物研究部門に、今珍しい研究材料が入ったところなのだけど………」
麓が言うと、快は周りを見渡す。
「あれ? グリードは?」
「そういやいねぇな」
棕と共に、首を左右に揺らし、麓も快もグリードの姿を探した。
しばらく、少しの混迷に快と棕、麓が身を動かしていると、どこからともなく獣の咆哮が轟く。
咆哮は、獅子の如き猛々しさと、蛇の声のような胸の凍り付く余韻、山羊の断末魔を思わせる恐ろしさを秘めていた。
「この声! まさか“実験体”が逃げ出したか!!」
麓は快と棕をガラス張り部屋たちの、連なる空間に置いて、奥の扉に向かって走り出す。
向かった先は“禁忌生物研究部門”。
快と棕も、それに釣られるように走りだしていった。
「おいおいおい、何があったってんだよ!」
棕は印章封印札を握りしめ、念じて衣装を身に纏う。
快は、走る中でただ固唾を飲みつつ――これから起こりうるであろうと予感させる“こと”に覚悟を決めた。
快らが入った先は様々な液体とフラスコ、書類が床に散らばっており、壁には銃弾の痕跡が夥しくつき、もはや単なる事故によるものでないことが明らかだった。
そして、その空間の奥の扉から――麓の体が、吹き飛ばされるかのように飛んできた。
快は、それを受け止めようと大の字になって身構える。
しかし、麓の体の重さに耐えきれず、快の小さな体は床に着いた。
「大丈夫、ですか!?」
声をかける。
だが、反応は――無かった。
快がふと、自分の両手を見る。
快の横で、棕は、呆然と立ち尽くしていた。
扉の、奥にいるものを瞳に据えて。
「なんだよ、アレ…………」
快は、背中を起こして正面を見つめる。
正面の破壊された扉の奥には、信じがたいものが居た。
ありえない、と声に出さざるを得ないような姿の魔獣が、青と赤紫の瞳を爛々と輝かせていたのである。
魔獣は、猛禽の翼を背中に生やしており、その間には山羊の頭が飛び出し、尻尾は蛇の体と頭、本体となっているであろう胴体・足・頭はライオンのそれ。
魔獣の足元には、Fencer隊員のものと思しき遺体がじゅうたんのように広がっていた。
その末路は、苦悶に満ちたヘルメット越しの隊員の表情とバラバラになった体が語っている。
快は、その魔獣を前にギリシャ神話の大怪物を想起させた。
「獣の魔王、キマイラ………!!」
名を告げると、魔獣は咆哮する。
快は、魔獣を前に身構える――。
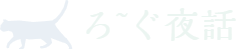


コメント