私は、夢を見た。
天から梯子を伝って、延々と降り続ける、そんな夢。
雲を抜け、光射す空を見渡す事無く、ひたすらに降りていく。
ふと周囲を見てみれば、雲の天井から落ちていく何者か達の姿が見える。
落ちていった先は人間の手を組み合わせたものとも、彼岸花とも取れない、薄緑がかった白い花のようなものが待ち構えており、何者か達がその中央に入ったとたんに―――光を孕んで包みこんでいった。
私が無我夢中でその下へ続けなければいけない気がして、忠実に降りていくと、やがて赤黒い空間が広がる。
そこを通過すると、全くの暗闇に等しい場所へと辿り着いた。
どくどくと脈打つかのような音だけが響く、その暗闇の空間に対しては唯一、私は降り続けなければならないという使命的な脅迫観念さえも、握り潰してしまうような恐怖に駆られた。
梯子を伝って上へあがろうとすると、私の手は、梯子からするりと抜け落ちていった。
空中でもがいていると、あの謎の者達が包まれていた薄緑色の物体が、私の体を乗せる。
薄緑色の物体の掌の上に乗せられた際、私の動きはまるで一切封じられたかのよう身動きが取れずにいた。
そして、薄緑の物体は私の体を持ち上げ―――奇妙な黄色い後光が煌めく、青白い手の前へと差し出した。
青白い手の前に行くと、私はますますの恐怖が身を襲った。
それの前に居ると、私の肺が収縮を繰り返し、酸素を全て吐き出し、内臓の機能の悉くが停止するかのような感覚がしたのだ。
にも関わらず、薄緑の物体は私を乗せたままに青白い手の前へどんどんと近づいていく。
私の意思は、青白い手の中で消えるわけにはいかない。と、心の中で―――何度も荒い息を吐き出しつつ唱えていると、私は気が付く。
その青白い手は、私自身の手だった。
一体いつ目が覚めて、どこからどこまでが夢だったのかさえ今でも判別がつかない。
しかし、鮮明に強烈な体験として私の脳裏と瞼に、今でも焼き付いて離れずにいる。
私は、その記憶に関して―――夢と、現実が直接的に幻覚のように繋がった瞬間だったのだ、と思いたい。
今後、こういった幻惑と夢の分別のつかぬものを見無いことを切に願わんばかりである。
ところで、私はいつ、最後に眠りについたのだろうか?
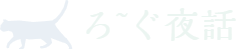


コメント