ことの始まりは、魔王の進軍だった。
嵐の如く、この世の終わりが訪れたかのように王の国が蹂躙されていく。
避難してきた遠くの地方民から、僕の地元が焼かれ崩れていったと聞いた。
母の居た、森の住民たちがたった一体の強大な魔物に殺されたとも聞いた。
転移魔術を使って逃げ延びた、別の地方の住民たちの様を見て僕は、騒ぎを収めるために王宮の地下室へ案内していく。
上の階で、暴れる王の体を抑える兵のうめき声が聞こえる。
窓の外を見れば、魔物達の軍勢に、銃や魔法を使って抵抗を試みる王宮魔術師達や兵士達の姿が見えていた。
必死に戦い、魔物達の手によって死体に変えられ、あるいは魔物達の死骸が積み上がって行く光景は、戦いの苛烈さを如実に物語っている。
戦火に包まれた街は見るも無残なありさまで、ついさきほどまで栄華を極めた大都市、城下町の末路だということが信じられない程だ。
建物を彩るは、今や逃げ惑う人々の亡骸と血しぶき。
道に並ぶは一糸乱れぬ兵隊達の凱旋ではなく、混沌極まりない魑魅魍魎共の行進。
(もう、救いはないねぇ)
ため息をついて、僕は王宮内の食堂での食事を終えた。
足元に転がっているのは、窓ガラスを突き破り飛ばされた兵士達の骸。
これが酒に潰れて寝転がっているだけなら、どれほどよかったろう。
そんな刹那の妄想を、目の前の兵士たちの胸や頭に突き刺さった武具の破片が、無慈悲に消し去る。
(僕も、王に言われた通り地下へ移動しようかな)
僕は、ただの王宮錬金学術師。
前線で戦う事も、命のやり取りをすることもない。
僕の父は国宝とまで謳われた伝説の鍛冶屋、母はエルフの薬剤師。
親の七光りが幸いして、王宮へ入ればサラブレッドともてはやされたはいいが――ひたすら日々が退屈だった。
強いていうのであれば、今闊歩している兵隊たちの聖銀の兵装、王の義手義足と鎧をこさえ、王の使っている短剣を復元させたのが楽しかったぐらいで。
王宮錬金学術師というのは退屈なもので、鍛冶屋が作った鎧や武器などの武具の解析と必要に応じた強化、魔力の込められた鉱石を利用し薬学や魔術に転用できるか否かを探ぐるものが主な業務だ。
僕の場合、幸か不幸か父の武具作成技能を教わり、薬学についても母譲りの知識を持っていたので――この大都市で、錬金学術師としての仕事、薬学と武具作成・強化の仕事をこの身一つに請け負う事になっていた。
多忙極まりない、その癖機械的で―――つまらないものだ。
知識と技術を授けてくれた両親は、今頃どこで何をしているやら。
なんて。
僕は階段の裏の、地下へ続く隠し階段へ向かった。
隠し階段を降り、扉を開ければそこは地下室というよりも大空洞という方が正しい空間が広がっていた。
奥は延々と暗闇が広がり、左右を向いてもどこが壁かすらわからない始末。
それほど広い空間にも関わらず、それを埋め尽くすほどの人が居た。
人々は互いが邪魔だと言わんばかりにひしめき合っており、すし詰めの状態だった。
「失礼、僕もいれておくれ」
僕が入り込むと、皆狭苦しく互いを圧迫しあい、もはや僕の居場所すらないと言わんばかり。
やがて、上の階から兵士の悲鳴と――我らが王の怒号が聞こえてきた。
王がよほど激しく戦っているのか、天井からほこりが垂れてくる。
それだけにとどまらず、しばらくして天井が震えだす。
金属音と、共に。
王は、最強の人間だ。
巨大な体躯に、これまで倒してきた魔族の脊髄をつなげ、王族の服の上を飾っているのがまさしくその異名に信ぴょう性を持たせる。
きっと、今度の戦も王が暴れ――人類が勝利するだろう。
王の魔界侵攻の話、反乱軍によるデモ、とある村でのこと。
勝ってくれないのなら、さっさと亡国の一学術師としてこの世界から身を消すのみ。
僕の退屈な人生が、幕を下ろすだけ。
僕は、目を瞑る事にした―――。
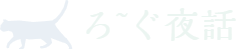


コメント