寛大聖教と呼ばれる、宗教の信者に連れられるままに、一行は歩む。
心地よさげに、雲一つなく照らす青空に、似つかわしくない疑いの感情を――今まさに一行を先導する信者に向けて。
黙って、ただ黙って足を進めていく。
全身に力を入れ、地を踏みしめて。
一行の脇に茂げる田んぼを撫でる風に、髪を吹かれながら。
「…………どこまで行けば、あんたらのアジトがあるんです?」
棕は固く閉じていた口を開いた。
「もっと、もっと先です」
女は振り向いて、頬肉に押し上げられた目を棕に向け言う。
棕が頷くと、女は再び足を動かしていった。
それと同時に、一行の歩みも動いていく。
しばらく歩いていると、やがて巨大な――――教会の扉の前へと着いていた。
「お客様です、お開け下さいまし」
女が扉を叩くと、扉に魔法陣が浮かび上がり、扉が勝手に開いていった。
魔法陣は、緑色に妖しく輝き、扉が開いていくと同時に輝きを失っていく。
それは一行にとって、これまで見てきた魔法陣の中でも特に不気味かつ、不条理なもののように感じさせた。
教会の中――そこは異空間としか言いようがない、重圧的な空気が広がり、それと共に異臭が立ち込めている。
内装はとても殺伐としており、荘厳でありながら独特の蛸の触手をあしらった椅子や壁の装飾が目立っていた。
一行の眼前の左右には、椅子に座った白装束の者がひしめき合っていた。
女が奥へ奥へと進んでいくと、後ろで並んで歩いていた快がふと踏みしめている床に目を落とした。
その床は、カーペットが敷かれており、カーペットは紫色のラインを中央に描き、ラインの両端は深緑色に染められていた。
教会内に立ち込める、奇妙な非現実的違和感、教徒と思しき人間達の視線とカーペットの感触。
空間の中で体験する全ての感覚が、快を含む一行に、未知の恐怖感として身を焦がしていった。
「さぁ、来ましたよ。教祖様」
女が祭壇の前で、声を響かせて言うと、祭壇の奥に立っている白装束の男が念仏の様なものを唱えながら――背後を振り向き、女と一行の前に顔を見せた。
「これはこれは―――何かのご縁でしょうか。これもまた主の思し召し」
男は両腕を広げ、祭壇から降りはじめると女は一行の先頭から逸れ、退いていった。
(こいつ……………かなりやばい感じがする)
棕は男を警戒した様子で、歯を食いしばりズボンのポケットの中のカードを強く握りしめる。
「迷える子羊たち、幸薄き子――あなた方と会えたのはこの主の”紋”のお導きに違いありません。どうぞ、紋をお見せください」
「私はネーブ、ネーブ・ブロード。主より賜った寵愛を与える使命を全うしたく思う者です」
男は胸に手を置き、懇切丁寧にお辞儀をした。
ネーブの外見は、長身の老神父といった出で立ちで、金髪の髪には白髪が混ざっていた。
安心感を覚えさせるような態度と穏やかな口調に、快・アイネス・棕の三人は一層身に力を入れていた。
「紋って、何ですか?」
快が問うと、ネーブは再び礼をして語った。
「我々は、この”紋”が何よりの主に選ばれしものの証明としているのです。では失礼して――」
ネーブが首元の襟を思いきり下へ下げると、そこにはびっしりと―胸鎖乳突筋から鎖骨にかけてに快と同様の痣が浮かんでいた。
「これがある者は、選ばれしもの――即ち、進化の権利を得た者なのです。あなたにも、それがある様子。さぁ、お見せください」
ネーブが笑みをたたえながら手を差し伸べると、快は更に質問を続けた。
「待ってください。進化の権利ってどういうことなんですか? 何を目的としているんですか?!」
ネーブは、ゆっくりと、まるで親が子供に言い聞かせるような口調で答える。
「では―――まずこの我々が活動するに至った経緯をご説明しなければいけませんね」
「我々は願っていました、不老不死の肉体を」
ネーブがそう言うと、一行の後ろで座っていた教徒たちが一斉に立ち上がり、続けるように言う。
「我々は求めていました、永久の恵みを」
教徒たちが息を合わせて言うと、ネーブは頷き唱える。
「我々は恐れていました、魔や天の使いを」
「我々は、憧れていました――愚鈍なる人種の終焉に」
教徒と、ネーブが交互に言うと、ネーブはその場で腰を深く曲げ――快に目線を合わせた。
「――かつては、封印された神話としか伝えられなかった”二つの禁忌”。四十年程前に、蘇らせることに成功したのです」
「悪魔の契約の力を用い、あらゆる神の力を行使し、魔術書を読みふけ試す毎日でしたが――とうとう、悪魔の肉体を支払い、神の魔力によって主がお目覚めになられたのです」
ネーブが全てを語り終えると、満面の笑顔で快ににじり寄った。
「主も、人類が進化し、魔族よりも強く、天の使い達よりも高尚なる精神に目覚める事をお望みなのです。我々はその始まりに、新たなる創造神話に立ち入っているのですよ…………」
(………つまり、この痣が、進化するべき人間の証だとでもいうのか? だとしても何故寿命が縮むなんてこと、こんなデメリットが背負わされるんだ?)
快はネーブの顔を背け、ほんの一瞬、思考に耽る。
快が思考していると、ひたすらに黙っていたアイネスが口を開いた。
「待って、その印がつけられると大抵は弱って死ぬ。なのに何故あなたたちは生きているんです?」
アイネスの発言に、周囲はざわめきだす。
ネーブだけは変わらず、笑顔で言う。
「主はえりすぐっているのですよ、真に選ばれし者を」
「じゃあ――案内してくださったレディは、どうやって印を受け取ったんですか」
アイネスの指摘に、ネーブは深く息を吸い込んだ。
「―――あまり、外部の方にはお見せできませんが……………もし、我々と共に活動を支援してくださるのであれば、方法をお見せしましょう」
ネーブが手を組み、祈るような仕草を見せると――祭壇の奥の逆十字が音もたてずに自然と開いていった。
あたかも”逆十字”――否、教会全体が生きているかのように。
「いかがいたしますか?」
試すような口ぶりだった。
快が何かを言おうとすると、棕が代わりになるかのように言う。
「あいにくと、快とアイネスはあんたらには付き合えない。だから、うちだけでいく。たかが一人、部外者が入って口外したところで何にも影響はないっしょ?」
「おやおやおや……………奇特な申し出ですね」
「あんたらは多分、危篤かもしれないけどね」
ギザギザとした歯をちらつかせ、棕は勇んで返す。
そんな棕にネーブはただ、余裕をもった様子で棕に礼をした。
「では、くれぐれもお気をつけて。我々にとっても、手に負えない空間ですので」
「手に負えない……………中に何があるんだ?」
棕が訊ねると、ネーブがはじめて眉をひそめて返す。
「…………”主”へ歯向かったもの達と、主への贄とだけ言っておきましょう」
「待ってください! 棕さん…………」
快が引き留めるべく手を取ると、棕は頷く。
「大丈夫、いざとなったらアムドゥも居る…………多分、無事に帰ってくる」
棕は振り向きざまにさっと快の頭を撫で、奥へと進んでいった。
棕が奥へ進んでいくと、そこには仄暗い空洞が続いていた。
空洞は狭く、湿っており天井からは水の雫が滴り降ちている。
(…………まじかよ)
更に、奥へ。
奥を越え、深層へ。
深層を越えた先に待っているのは、深淵。
やがて、夜目が効いてきた状態でも自分の姿が確認できない程に奥へ進んでいくと―――遠くからぼんやりとした光が棕の目に届いた。
(やっと、目的地かな)
光へ向かって直進すると、棕は光の正体が見た事も無い、光を放つ壁画ということに気がつく。
(なんだこいつ?)
壁画を見ると、その壁画に記されていたのは黒い人型と、白い人型の何かだった。
両者はなにやら、円柱状の檻の様なものに閉じ込められており、黒い人型は檻から出ている様が描かれていた。
棕が空間の続く方へ進んでいくと、似たような壁画があった。
そこで思わず、棕は引き込まれる様に壁画へ飛びついた。
今度の壁画では黒い人型が、棒状のものを手にしているのに対して、白い人型は、檻の中で閉じ込められ、多くの人型に見つめられている様が描かれていた。
(黒い人型は、優遇されてたってことか? じゃあなんで白い人型が閉じ込められて――いや、”何故両者とも閉じ込められている”んだ?)
(そもそも、なぜ日本にこんな壁画が……………?)
怪しく光を放つ壁画から離れ、棕は探索を再開した。
すると、奥から獣の咆哮のような轟音が響いた。
『ガアアアアアアアアア!!!!!』
(何!?)
棕はズボンのポケットからカードを取り出し、すぐさま衣装を着替えアムドゥシアスを召喚した。
「アムドゥ、いきなり呼び出しといて悪いけどここ、かなり危ないみたい」
口とは別に、肝が据わっている様子で語るが、呼び出されたアムドゥシアスは目をせわしなく動かしていた。
「アムドゥ? どった?」
呼びかけると、アムドゥシアスは声を震わせる。
「ここから、すぐに逃げたほうがいい!」
「……………いや、今更引き返せないっしょ。大事な情報源だよこれ」
アムドゥシアスに真剣な眼差しを向けると、アムドゥシアスは目を逸らして返した。
「奥から、莫大な魔力を感じます……………ワタクシでも、この後に起こることがどうにもできない気がしてならんのです」
「どうにかしてみせるのが、プロっしょ」
棕は、咆哮の聞こえた方へ進んでいく。
そして、待ち受けていたのは――――世にも恐ろしい光景だった。
十字架に、様々な姿の怪物が磔にされていたのだ。
「……………は……………………?」
アムドゥシアスは、絶句した。
その磔にされた怪物たちの、錚々たる面々に深い絶望を覚えたように。
「テュポーン様………エキドナ様………パズズ様……………アスモダイ様………………?」
アムドゥシアスは、棕の後ろで膝をついて、十字架を眺める。
「知ってんのか?」
涙を流しながら、アムドゥシアスは答えた。
「知ってるも何も、魔界では有名な魔王の器の方々…………本気になれば、地上界の文明全てを滅ぼせるほどの………………!」
棕は、スマホのライトを起動し、光を十字架に当てていった。
(そんなやつらが、なんでこんな目に!? 全員血だらけじゃねぇか!)
「そこな……………人間……………………私の話を……………………聞くのだ」
声のする方を向くと、瀕死寸前の悪魔属――テュポーンが居た。
「………良いか、私はかつて神々に抗い、勝利した。今でいえば、ギリシアにて語られる魔族の初の勝利だった」
「強大な神を前に圧倒した魔力とこの力…………これを以てしても、やつには抗いようが無かった」
テュポーンは、口から血のように、小さな蛇を吐き出しながら言い続ける。
「我が妻、エキドナもやつと戦った。元はと言えば、あの小僧の口車に乗ったのがいけなかった」
「………………人間よ、貴様らは絶対にやつと戦ってはいかん。神であろうと、いかなる英雄だろうとやつは止められん」
「やつやつって、お前そんなに喋って大丈夫なわけ?…………むぐっ!?」
見上げて棕が言うとアムドゥシアスが焦った様子で口を塞いだ。
「アムドゥシアスよ、気をつかうな。……………………私らをこんな目に逢わせたのは、”ジェネルズ”という名前の……………怪物だよ」
「ぷはっ、ジェネルズ……………? そんなに強いのか?」
棕はアムドゥシアスの手を振り払い、問う。
「あいつは、神でも魔王でもない。だが、不条理なほどに強い。あんなやつを封印できた者の顔が知りたいわ」
「…………人間、なぁ人間よ。矮小なお前らに頼むなど反吐が出るが…………もはや我が身に宿った生はあとわずかだ」
テュポーンの脚には、タコの様な痣が発現していた。
そしてそれは――他の怪物たちも同じだった。
棕はそこから、推理した。
(まさか、そのジェネルズってやつがこの病の原因なのか?!)
「頼みがある」
「…………何?」
棕が反応を示すと、テュポーンは涙を流して――訴える。
「やつに挑んだ我が娘の……………………安否が知りたいのだ」
「娘の名は、キマ―――」
名を言いかけた瞬間だった。
テュポーンの首が、宙を舞ったのは。
「ひいっ!? テュポーン様!?」
アムドゥシアスが驚愕していると、”首を狩った者”の正体が棕の目の前に現れた。
「はろー♪ …………いやあ、テュポーンのおっさんも頭が下がる思いだってさ」
グリフォンの翼をもった、悪魔属の姿。
「…………どういう、おつもりで」
アムドゥシアスは、固唾を飲みこみ、悪魔属へ言う。
「……あんた、ナニモンだよ」
棕が睨むと、悪魔属は手に持ったテュポーンの首を離した。
「……………………あたしっちは、地獄から戻ってきた悪魔。シトリーちゃんだよ」
名乗りを上げると、シトリーの背後で磔にされていたアスモダイが怒鳴り声をあげる。
「!! そこにいるのかペテン師!! 貴様よくもよくも実の父まで―――」
シトリーが後ろを振り向いたかと思えば、刹那。
アスモダイの首も、飛んでいった。
「……………シトリー様、どこでそんな力を」
「ちょっと、あこぎな事覚えちゃったんでね」
そう語り、妖しく光るシトリーの瞳は、まさしく獣よりも恐ろしい何かが宿っているかのようだった―――。
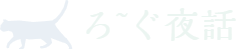


コメント