「バアルゼブル! バアルゼブル!」
バアルゼブルは霞む目を、聞き馴染みある声に答え、無理矢理開ける。
「うぅ…………あ、アニー…………」
目の前で、心配そうにアナトはバアルゼブルの頭を撫で前髪を流す。
「何があったの? ゆっくりでいいから話して」
潰れた胸を、脈打たせバアルゼブルは語る。
「村人たちにも…………伝えて、竜教の人間達が三日後に僕らを攻撃しに来るってっ…………ぐふがあっ!!」
伝え終えると、バアルゼブルは咳き込み口から濃く深い、緑色の液体を吐き出す。
バアルゼブルの体を構成する、蠅の血液である。
「解った……バアル君は神殿で休んでて」
「ししっ…………悪いけど連れてってくれない?」
口許の液体を拭い、アナトはバアルゼブルの体を持ち上げ、神殿まで浮遊して運んでいく。
道中、バアルゼブルの体から潰れたハエがぽとぽととこぼれながらも。
洞窟内へ着くと、アナトはバアルゼブルの体をそっと置いた。
乱れた呼吸の、夫を前にアナトは拳を震わせる。
洞窟に響くのは、戦の女神の鉄拳の鳴る音。
「……許してたまるか、異邦人の侵略者共が」
アナトは歩いて洞窟を出て、村へ向かった。
すると、村の門には重たそうに籠を携えた村人たちの姿が見えてきた。
村の門の奥に居るアナトに気付いた様子で、村人たちの先導をしていた若者が声をかける。
「おおアナト様! ご覧ください! 都市から新たに種芋を仕入れていたのです! もちろん新しい果物と肥料も__」
和やかに語る若者に、アナトは激昂で返す。
「…………豊穣神からの命だ!!来る外来人に備えてっ!!」
唐突的な、アナトの怒りが混じったような声に若者は籠の重量もあいまって腰を抜かす。
「なっ………何をおっしゃるのですか? ここは辺境の地ですよ、外来人が来るなんて__」
「なら、アタシのバアル君がなんで傷ついてるの!? バアル君が言ったことは絶対なの!」
狂ったように声を荒げ、アナトは腰を抜かしている村人に言い寄る。
「竜教の人間が、この村を滅ぼしに来るってバアル君が言ってたの」
竜教 という言葉を聞き列の奥に居た村長が反応を示した。
何かを、知っている様子で。
「なんと、竜教ですと…………!?」
「知ってるのですか?」
村長は、蓄えた髭を撫でながらゆっくりと、手を震わせながら語る。
「うむ…………眠りについている古代からの守護神を信仰している宗教でな…………今ある元素、属性の産みの親なのじゃ」
「竜が守護しているのは、己が眠りについている大陸だという。竜に身と心を捧げる事で莫大な魔力と、来る”災いの日”からの救済が約束される という考え方の連中じゃ」
「この地には、金剛竜が眠りについているという。ならば恐らくは金剛竜を信じる宗派の者だろうよ」
若者は村長の方へ振り返り、訊ねた。
「それならば、何故攻撃するのですか」
「………竜教にとって竜たちの意思としている教えこそが全てだ。それ以外の神を信じる者や竜以外の神々は悪魔でしかないのじゃ」
淡々と語る村長にアナトの出会い頭の訴えを重ね、村人たちの額からは汗が流れていた。
「待って、なんでそんなこと知ってるの?」
アナトは村長に訊くと、村長は胸元から何かを取り出しながら答えた。
「竜教は、世界的にも有名な宗教でしてな…………二年も費やして行った今回の都市も、竜教を国教としていました」
胸元から取り出したのは、ロザリオだった。
「これがないと、検問が通れない始末でして」
ロザリオが無ければ、街へ行く事すら叶わない。
それは、竜教の強大さを如実に示していた。
「…………そんな奴らと、戦うというのですか?」
唾を飲み込み、恐れに震えた様子で若者は言った。
「………我らが神を傷つけたのだ、女子供は村から逃がして、異邦人どもに我らの信仰を示してくれよう」
「そうだよ、遣ってしまえ。アタシが命の保証をするし、アタシが力を貸す」
「バアル君を傷つけたお礼は、ただの戦死で済ませないから。__八つ裂きにしてやるッ!!!!」
夕暮れ時、太陽と共に女神の静かな怒りが燃えていく。
その焔は、やがて人々に燃え移る。
両方に訪れるのは、暗闇とは誰が知ろうものだろうか。
「あいたたた…………ちょっと治ってきたかも。…………あれアナト?」
バアルゼブルが目を覚ますと、洞窟内の視界は一面暗闇に閉ざされていた。
体は、既に癒えていた。
バアルゼブルは体を起こし、洞窟の外へと飛び立った。
洞窟の外へ出ると、夜の帳が下りていた。
入口から見渡すと、村の民家には明かりが灯っている。
(? 帰ってきて疲れてるだろうに夜更かし? 何が起こってるのだろう)
バアルゼブルは体を分裂させ、ハエを村中に放ち、拡散させた。
その一匹一匹は、民家の中に入り込んでいった。
そこには、荷造りをする親子の姿や、槍と思しきものを作っている男、膠の鎧を作っている者の姿が見える。
「ねぇ、神様を置いてっちゃうの?」
その中の親子の家にいる子供は、壺を持つ母親の服の裾を引っ張っている。
「いいえ、我らがアナト様がいるんですもの。 ただのしばらくだけの引っ越しで済むわよ」
言い聞かせるように、母親は壺を隣に置き子供の頬を撫でて言う。
「でも、竜教って強いんでしょう? お父さんも、大丈夫かな。バアルゼブル様も…………」
「大丈夫、大丈夫よ」
母親は子供を力一杯に抱きしめながら、今度はささやくように言った。
(…………今、この人らから何が起こっているか聞くのは酷かな。そっとしておいてあげようっと)
しきりに手をこすり、バアルゼブルはその場から撤収した。
一方、木の棒を削り槍を作っている男の家では、独り言が聞こえていた。
「何が竜教だ、クソったれが。俺たちの何が気に食わねぇってんだ…………そんなに気に食わねぇなら直接タイマン張ってやらぁ」
棒を削り終えたところで、男は自分の隣に置いている、尖った石を先端にあてがう。
「だめだ、持ち手の部分ももう少し削らねぇと滑るな」
「こんばんわぁ、今日はあいにくの曇天だねぇ」
ハエの群れが渦上に集まり、バアルゼブルは男の前に姿を現す。
窓に座って。
「ねぇ、なんで武器なんて作ってるのさ」
バアルゼブルは棒に指さして問う。
「アナト様と、村長の命で………来る竜教の者への備えとして作っているのです。バアルゼブル様も、どうかご加護をください」
「へぇ。………それで、頑張ってね」
にこりと、笑みを浮かべバアルゼブルはその場から去った。
(アナト…………まさか)
村中を回っていたハエは、村の広場へ結集し元の姿へ戻る。
村の広場には、腕を組み、鎧兜に身を包み、巨大な斧を持つアナトが居た。
「アナト、これはどういう事なの?」
アナトの背後で、バアルゼブルは聞く。
「! バアル君傷は大丈夫なの?! 二日間も寝てたけど…………!」
バアルゼブルの姿を見てアナトは嬉しそうに、兜の中で声を反響させる。
「二日間……か。僕は大丈夫。それよりさ、村人たちになんて言ったの?」
「そうそう、バアル君を傷つけた愚かな竜教がまた来るから__」
「”根絶やしにして返せ” って言ったの」
兜の中で妖しげに、狂気を孕んだ瞳を輝かせアナトは告げる。
バアルゼブルはその様子を見て、顔を青ざめさせた。
「え………じゃあ、例の村人たちの戦闘準備、避難準備って…………!」
「そう、みーんなきみの為にって躍起になってるの」
アナトの発言に、バアルゼブルはその場で膝から崩れる。
「僕は…………ぼくは……みんなににげろっていみで…………!」
ふと、バアルゼブルは自身の記憶を振り返る。
思えば、自分は竜教が来る としか伝えていなかった。
弱り切った姿で。
それが、アナトの戦意を駆り立てる引き金となりえることを、何故考えていなかったのか。
何故、逃げろという伝言をしなかったのか。
バアルゼブルはもはやただ、瞳孔を震わせることしかできなかった。
「心配しないで、アタシが全部やっつけるし……これも全部きみの為だから」
アナトは、震えるバアルゼブルに恍惚としながら頬を擦った。
「………ししっ、そっかそっか。君の事、もっと考えるべきだったね」
バアルゼブルはその場から立ち上がった。
「僕は、自分勝手さ。周りの事、大事だと思ってると言っときながらなぁんにも考えてない」
アナトの頭を撫でた後、兜を脱がしバアルゼブルは唇に触れる。
アナトは、状況を掴めておらず戸惑いを見せていた。
「今更、戦を止めろって言っても聞かないんだろ? 君の事だ。………だったら、少し待ってて」
「…………バアル君?」
バアルゼブルがアナトから離れ、村の門へと向かう。
「朝になったら、みんなでお祝いしようねっ。題して”不戦勝記念”なんて、ししっ」
体を散らせ、アナトの前から姿を消す。
蠅の群れは、門の先へと向かっていった。
村の門の先には、なだらかな一本道があり、その両脇には木々が離れ離れに生えていた。
村から六キロ離れた先に生えていた木の枝に、バアルゼブルは座った。
(みんなに、痛い思いもしてほしくないし、みんなの事が危険視されればまた集中的に攻撃される。………ならこうするしかないかな)
段々と、朝焼けが大地を照らし始める。
欠伸を抑えながら、バアルゼブルがじっとその場で堪えていると、銀の鎧を装備した集団が道の先から見えてきた。
音を立てて、近づいてくる集団にバアルゼブルは木から下り集団の前で立ちふさがった。
「おはよっ、こんな朝早くからご苦労様」
「!! 悪魔だ! こいつが司教様を襲った悪魔だ!」
若い集団の一人が慌てた様子で剣を構える。
「襲った? 襲ったのは君らじゃあないかあ~、ししっ」
バアルゼブルがそう言うと、先頭のマントを付けた鎧の者が剣を振り上げる。
「おっと、危ないって。……お願いだから、ほっといてくれないかな。僕は少なくとも君らを傷つけたくないんだ」
必死に伝えるが、会話にすらなっていなかった。
やがて、集団は何かを呟きだす。
それは、村を襲った男のそれと同様のものだった。
「既に貴様の存在は、国中に知れている。”蠅の王”としてな! 村から逃げ出そうとしたみたいだが、もはやどこにも逃げ場はないぞ!」
魔術を展開しながら、集団の一人が言った。
「……あだ名のセンス、お母さんのおなかからやり直した方がいいんじゃない? 頭に栄養足りてる?」
空中を浮遊し、バアルゼブルは集団の言葉に嘲笑を送る。
すると、集団は一斉に頭上に形成した岩石を放つ。
しかし、その全てはバアルゼブルが腕を振ると軌道はバアルゼブルから逸れていった。
「引き返せ、立ち去れ。僕の願いはそれだけだ」
「………所詮、糞の山の大将か」
マントを付けた鎧の男が、呟く。
すると、集団は一斉に笑った。
「……ちょっと、僕年のせいかな? 聞き取り辛くってさ」
バアルゼブルの顔が曇りを見せる。
それを見て、マントの鎧の男は決して見えぬ笑みをたたえた。
「攻撃をせず、結局は臆病なだけじゃあないのか? 人間の報復を恐れているのか?」
「おまけに、自分が支配するのはまるで糞の山のように文化が遅れに遅れた、肌の黄色い異人ども。蠅の王という名前も相応しいだろう」
侮辱の言葉に、バアルゼブルは次第に沈黙していく。
「否定すらできんか、耳障りな羽音すらしなくなったじゃない__」
マントの鎧の男が、次なる台詞を言おうとした瞬間、バアルゼブルの体は消えた。
集団は周囲を見渡すが、その場にはバアルゼブルの姿は無くどよめく。
そのどよめきは徐々に、静かなものへと変わっていった。
そして、集団の内の五人は気づく。
一つは、集団の数が減っている事に。
もう一つは、残されたのは、我々だけだということに。
最後に、その集団の行方。
やっと現れた蠅の群れは、元の形を成すと、その手には頭蓋骨が握られていた。
口許には、肋骨の一部と思われる折れた骨が咥えられている。
瞬時に起きた惨劇は、緑色の毛髪をしていた敵の頭部が、黒みを帯びた赤に染まっている事で示していた。
「ねぇ、君らってさ、こんなに…………くっさくて不味いの?」
バアルゼブルは肋骨を噛み砕き、咀嚼し飲み込むと腕を散り散りにさせ、頭蓋骨を消滅させた。
「ひぃぃぃ!!!」
そのおぞましい光景に五人は腰を抜かす。
「群れをなして、穏やかに時を過ごす者に害を与え、甘い汁だけを啜り強い者の前ではゴマをする」
「本当のハエ ってどっちなんだろうねぇ」
バアルゼブルは腰を抜かしている一人に近づくと、その一人の腕を撫でる。
すると、みるみる内に中身だけが消滅していった。
バアルゼブルが、喰らっているのだ。
「あーもう、まずい。骨も食べてるけど、なんで君らって中身もこんなに酷いんだろうね」
「助けてください…………俺には病気の両親が居るんです………!」
またある一人は、その場で泣きつき命乞いをした。
それに釣られて、残る三人も跪いていった。
「お願いです! 神様!」
「もはや神とはあなた様しかおりません! どうかお慈悲を…………!」
投げかけられるのは、先ほどとは打って変わった懺悔の言葉の数々。
バアルゼブルは、血の付いた兜を指で回しながら考え込んだ。
「じゃあ、もう二度と村に近寄らない?」
「もちろんですとも! ええ!」
返事を聞き、バアルゼブルは兜を思いきり地面に叩きつける。
すると兜はひしゃげる。
「ひぃ!」
四人は怯えて瞼を一斉に閉じていく。
やがて、死への覚悟を決めた時。
「…………おっけぇ、君らにも家族が居るし、僕もこれ以上無益な殺傷はしたくない」
「へ?」
聞こえてきたのは意外な返答であった。
「じゃあね、気を付けて帰るんだよ。あ、僕の村、襲わないならいつでも遊びに来ていいからね」
バアルゼブルは、その場から背を向ける。
(…………とはいえ、人を傷つけちゃった以上、このまま素直に帰れない、かな)
(悪魔の居る村として伝わってる以上、迷信にさせなきゃ…………みんなの身が危ない)
バアルゼブルは、魔法陣を展開する。
(……転移魔法を使ったはいいけど、どこへ行こうかな。とりあえず__)
魔法陣の中へと、バアルゼブルは消えていく。
その後、辿り着いたのは原初の魔界。
かつての豊穣神は、名を改め魔神となる。
かくして、蠅の魔王”ベルゼブブ”が生まれた。
__という”記憶”。
その記憶は、混濁し改窮された__本人の脳内で作られた偽典である。
真実は、残酷であった。
~true~
返事を聞き、バアルゼブルは兜を思いきり地面に叩きつける。
すると兜はひしゃげる。
「ひぃ!」
四人は怯えて瞼を一斉に閉じていく。
やがて、死への覚悟を決めた時。
「…………おっけぇ、君らにも家族が居るし、僕もこれ以上無益な殺傷はしたくない」
「へ?」
聞こえてきたのは意外な返答であった。
「じゃあね、気を付けて帰るんだよ。あ、僕の村、襲わないならいつでも遊びに来ていいからね」
バアルゼブルは、その場から背を向ける。
(…………とはいえ、人を傷つけちゃった以上、このまま素直に帰れない、かな)
(悪魔の居る村として伝わってる以上、迷信にさせなきゃ…………みんなの身が危ない)
そう思考を巡らせていると、四人は起き上がり、聞こえぬように詠唱を開始する。
そして、気づかぬうちに__銀の剣が投げられ、岩石はバアルゼブルの頭に降り注いだ。
その一撃は、バアルゼブルの後頭部に刺さり、岩石が追い打ちをかけ、やがて全身を潰した。
「やったぞ!!!」
「化け物を倒したぞぉォ!!」
男達は歓声を上げる。
「そうだ、二度と生き返られないように焼いてやろうぜ!!」
男の一人は、そう言い懐から酒を出す。
「いいねぇ!」
賛同する男は、詠唱を始め火打ち石となる石を出現させた。
一人が酒を岩石の周りに捲き、ある一人は火打石を打つ。
火打石から放たれた火種は、やがて岩石の周囲に燃え広がった。
「火葬してやってんだ、これで祟られることもないだろう!」
空には男達の爆笑が響いていった。
冥界にて、バアルゼブルの魂は運ばれていく。
潰され、焼かれた肉体は元の姿に近い姿に、冥界の炎によって作り替えられていき、魔界へと送られていった。
この時、通常一度死した者は”死を自覚したうえで転生し、意思のみを引継ぎ記憶を消去される”のだがバアルゼブルは、違った。
バアルゼブルは、自身が死んだことを自覚していなかった。
自覚できなかったのである。
その上、記憶を司る頭部への衝撃と転生によって記憶が、改竄されていた。
故に、中途半端な死の間際の記憶までを持ち込み魔界へと送られていった。
「ここは…………えと、転移…………したんだよね?」
記憶が改竄されていることを知る由も無く、そのかつての神は周囲を見渡す。
一面は、薄紫色の荒野。
遠くを見ると、そこには銀髪の容姿端麗な青年が、杖を携え金色の髪の角の生えた青年と戦っていた。
「…………なにやってんだろ」
神は、その者達に近づく。
「はぁ、はぁ、俺様はまだやれるが…………息上がってんじゃあねぇか?!」
「脳筋とは違って酸素の使い方が違うんだ私は。…………ぜぇ、ぜぇ」
間近で神は二体の戦いを蠅の姿で見ていた。
青年は汗だくになっているが、金髪の方は爪を立てて笑ってさえいた。
「ねぇ、何してんの~?」
二体の間に割り込み、彼の者は言う。
「………魔王選挙戦、第一回だ。てめぇは邪魔だ、どっかいってろ」
金髪はそう返した。
「ぼうや、これは遊びじゃないんだ。本気の戦いでね」
「じゃあ、こういうのってアリ?」
片手をあげる。
すると、どこからともなく雨が降った。
「? 水の魔術か。珍し…………」
「ベリアル!! この雨からよけろ!!」
ベリアルと呼ばれた青年は、それを聞きすぐさま脱した。
ベリアルの肩は、煙を上げて肉を露出させていた。
「強力な酸性雨…………あんた、なにもんだ?」
「ぼくかい?僕は__」
「蠅の王 さ」
「_____であるからして!」
ベルゼブブが目を覚ますと、そこはプエルラ城の会議室だった。
「聞いていたか」
小声で、隣にいたユンガが耳打ちする。
「うん、ちょっと懐かしい夢を見ながらね」
「いや、寝てるじゃないか」
ユンガの言葉に、ベルゼブブは笑って返す。
会議が終わり、ふとベルゼブブは空を見上げた。
真っ赤な、満月が魔界を照らしていた。
「………皆は、元気にしてるかな」
懐から、ベルゼブブはリンゴを取り出す。
「アナトは、あれからどうしてるのかな。………地上が落ち着いたら、会いたいな」
真っ赤な一噛みは、しっかりと歯に感触が伝わる。
やがて、舌の上は甘酸っぱさと、柔らかさの中に固さを残す。
その味に、故郷を重ねベルゼブブは過ぎた日々と、過ごした季節たちに思いを馳せた。
「ベル、あのさ」
聞き馴染みのある声が、頭上から聞こえてきた。
上を見上げると、ユンガの顔があった。
「ん」
「……君の故郷、だっけ? の料理を作ってみたんだ。 ほら、たまにはメイドたちだけじゃなく、僕も作らないとなって思ってさ」
「ししっ、僕味にうるさいよぉ? それに、こういうのもなんだけど田舎生まれだし、故郷の味なんて__」
「…………”ツフ”っていうんだって。あと、ホブスっていうパンも作ってみたんだ」
「良かったらこの後、僕の城に来な」
ため息交じりの声は、ユンガの声に潰されていった。
懐かしい温もりの雪崩が、ベルゼブブに振っていく。
「…………うん、ありがとね」
(……………………まさか、この姿になってあの味が楽しめるなんて、夢にも思ってなかった)
(早く、魔族も人間も仲良くできる時代になるといいな)
(そしたら、真っ先に______)
純粋な願いは、月の隣で、魔界の流星に乗せられていった。
その願望は、地上へと届くであろう。
なぜなら、大地だけでなく、人々の心を豊かにした、他でもない豊穣神の願いなのだから。
形はかつてとは違えども、その想いは決して変わらぬモノだから。
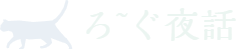


コメント