これは去年の秋から始まった事だ。
私の正気がまだ保てている内に、これを書き記そうと思う。
私は当時、住宅街に建てた二階建ての一軒家に両親と共に住んでおり、持病の為にいわゆる引きこもり生活を送っていた。
患っていたもののおかげで、苦しい思いをすることはあれども、それなりには幸せな生活だった。
―――唯、あることを除けば。
私は眠るとき、親と一緒に階段へ向かいそこを上って寝室へ入る。
その際、親には先に上っていってもらう事にしていた。
なぜなら、階段を上る時―――奇妙な感覚に見舞われるからだ。
奇妙な感覚、というのは親が背後に居ると認識しながらも、常に私の背後には何者かが居るという気配が付きまとっているというもの。
その気配を、少しでも軽減するための策なのだが、それでもやはり不快な感覚は消えず階段を移動するときには心持ち穏やかではいられなかった。
そういった感覚が、身を包む度にそれが妄想であることを切に願う。
そう思うほどまでに、奇妙な気配による、不快感は日常と化していた。
尤も、そのまま自覚せず、無垢なままにただ日々を浪費できていればよかったのだが。
あるときのこと、昼寝から目を覚ました私は小腹がどうしても空いていたので、一階に向かおうとしていた。
寝室のタンスに入れていた自分の財布を、カーテンにかけていたジャケットに入れ、部屋を出ると廊下は真っ暗だった。
時計を見れば、午後七時。
親は自分のベッドの隣で寝ており、穏やかな寝息を立てていた。
夕飯の残りがあるやもしれぬというわずかな期待を胸に、階段を下りていく。
階段は一歩一歩足を伸ばしていくごとに軋み、暗闇に包まれていることと、奇妙な追跡感が相まって私に言いようのない恐怖をもたらしていた。
早く降りねばならない。
でなければ、自分の身に”何か”が迫ってくる。
そんな焦燥に駆られ、親が寝ているにも関わらず大きな音をたてながら一階へと下り、冷蔵庫の扉を開けるとそこには何もなかった。
期待外れもいいところだ。
私が再び寝室へと戻ろうとした時。
足音が、私の背後に忍び寄ってきた。
私は急いで振り返ると、そこには―――なにも無く。
いよいよもって、妄想に加えて幻聴まで聞こえてきたか、と言い聞かせつつも呆れるように心の中で言い、階段を駆け上った。
扉をそっと開け、同様にそっと閉じ、ベッドの布団を自分の顔の方へ引っ張り上げる。
動悸を、誤魔化すように。
階段の方からは依然として足音が響きわたっており、むしろ――音は段々と私の方へ向かって激しくなりつつあった。
激しい音は、どうやら親には聞こえていないらしく、それがまた私の平静に戻そうとしている心をより乱す。
「私はきっと疲れているんだ」と心の中で呟き、目を強く閉じ込めた。
すると、一層音は強くなり――”音”がとうとう寝室の扉の前に迫ってくる。
音の正体と相対するかに思え、ぐっと目を瞑りしばらくすると、静寂が周囲を包みこんだ。
周りが静まり返ったのを確認すると私は、そのまま一呼吸で胸の中を整え、眠りに就こうとした。
その時だった。
天井から、物音が聞こえはじめたのは。
物音は、まるで巨大な―――人間程の大きさの”何か”が這っているような音。
聞いていて、不安感を煽るような音だった。
早く終われ、それか早く親が起きてこの音に気付いて。
目を強く瞑りながら、念じ続けていると――音は、消え去っていた。
安堵を胸に、ふと寝室の壁に立てかけてある時計に目をやる。
時刻は夜の八時を示していた。
よもや約一時間も音に悩まされることになろうとは。
悶えていた体を起こし、私は寒さからジャケットを羽織って寝室の扉をあけた。
扉の前には、やはりというべきか誰も居らず。
電気をつけ、階段を降りて軽食をつくろうと台所へいくことにした。
台所へ向かうと、台所の電気を付けていく。
冷蔵庫の中の玉ねぎと、コンソメスープの素を手に取ろうとした時。
伸ばした手には、切り傷ができていた。
血のにじむ左の手の甲を、流しにかけてあったタオルで拭うと、私は玉ねぎとコンソメスープの素の入った箱を取り出した。
身に覚えのなく、痛みを感じない傷。
しかし、先ほど起こった現象を前にした時よりも楽観的な思考で、気に止めることなく私は玉ねぎをまな板に置いた。
包丁は―――既に右手に握られている。
不思議と、その状況には納得がいった。
取り出した記憶も、ないはずなのに。
慣れた手つきで、玉ねぎを適当に刻み、水を入れた鍋の中に放り込んで、包丁を片付けてしばらく待った。
鍋の中が湯だつのが見えたら、私はコンソメスープの素を箱から取り出し、跳ねて踊る玉ねぎの中に加える。
スープの素が溶けていく事で、玉ねぎの入った湯は橙色に染められていき、完全なスープとなった。
スープが煮立つと、私は炊飯器をあけ、スープを茶碗によそい、白ご飯をその中に入れた。
いつもの、困った時の私の食事が完成したのだ。
熱いスープを食卓に置き、口に咥えていた自分のスプーンを右手に持つと、すぐに私は茶碗の中身をかきこんだ。
非常に熱いながらも、玉ねぎのとろりとした食感と、スープのうまみが染み込んだ白米が口の中に満たされていく。
それを飲み込むと、喉と胸を通して温もりが感じられた。
私のお気に入りの一品。
私はスープご飯を食べ終えると、食器を台所へやってすぐに私は寝室へと戻った。
寝室へ戻り、自分のベッドに戻ると――私は泥の様に眠る。
最後に見た時計の針は、夜の九時を刺していた。
目を覚ますと、寝室には誰も居なかった。
寝ぼけている頭を無理矢理起こし、時計を見ると朝の九時を示していた。
親の出勤時間は過ぎており、学校へ行かないのはいつものこと。
私は、階段を下りて朝食をとる事にした。
立ち上がろうとした瞬間。
足が、あがらなかった。
自分の体勢の問題かと思い、身をよじらせ、一回転させた後仰向けになると―――自分の足が目に映る。
カーテンの隙間から照らされた、白い足には昨晩の手の甲と同様の、切り傷が入っていた。
傷口は既にかさぶたとなっていたが、動かそうとするたびに痛みが響く始末。
そんな状態になってなお、記憶にない傷に対して私は特に違和感を覚えなかった。
異常であることは、自覚している。
それ故に―――段々と恐怖を感じていった。
まるで、幻聴と、妄想の中の”何か”と同化したかのようで。
症状をより自覚し、確信し始めてからの日々は、日常が異常に、異常が日常に感じるようになっていった。
空気の些末な変化、自身の感覚、おさまらぬ―――姿の見えないモノの居る気配。
やがて私の胸と行動には、日常の安寧を取り戻さんとするための猜疑心と、恐怖による脅迫的なまでの焦燥が現れていた。
でかけることもままならず―――気がつけば、家の側の電柱の前でただ茫然と立ち尽くし、時間が過ぎていたことさえあった。
いよいよ、引きこもりがちだった私は”自分”を守るために更に自室にこもり始めるようになった。
果ては、食事の際にスプーンやフォーク、箸といったものを使う瞬間にすら、気が付かぬ内に自傷行為へと走ってしまうのではないかと思う。
私は、挙句に食事をも摂らなくなってしまった。
電気を消す際にも、暗闇が目の前を包むと、気配は一層私に近づいた気がする。
”気配”が私から距離を詰めると、私の体を悪寒が走った。
電気を消すと、気配は遠のいた気がして幾分かは楽になり、部屋の電気は消せずにいた。
そして、ある日床に就き、布団をかぶっていると―――暗闇の中から声が聞こえるようにまでなった。
夜の八時の事。
声は私の名を呼び続けると同時に、あるはずもない視線を送る。
あるはずもない、ありえないと思いつつも――否定しきれない何かが確実に巣食っていた。
声は、あいもかわらず私を呼び続け、呼吸が乱れていく。
布団から飛び出ると、私の隣に置いておいたデジタル時計は午前七時を示していた。
時間の感覚、睡眠の感覚さえも心の中の”何か”によって失われていたのだ。
そう思うと、全てが嫌になり、こんにちまで眠らずに居る。
もう、最後に睡眠をとったのはいつだろうか。
人間的な感覚はとうに失われているが、今眠ってしまえば確実に”何か”に全てが奪われるような気がしてならない。
震える手をごまかし、今もペンを握っている。
だが、もうそれも限界かもしれない。
私の左手には、赤く染まったナイフが握られている。
開けた覚えのない部屋の扉も空いているし、目の前には両親が血まみれで横たわっている。
左手ガ、ワタシノノどヲ。
ノどってドコ?
ワタシて、なに?
まっか、まっか。
ぜんぶ、まっか。
なんにも、なかった。
さいしょから、ぜんぶ。
おかしいのは、ぜんぶ。
あついなぁ。
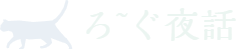



コメント