泡沫の夢を見る。
瞬きと共に消えゆきそうな、そんな望み。
いつからすれ違ったろうか。
誰にも知らぬ内に、滅びを望めば滅びずに。
生へ執着すれば、その執着の意味の全てを無へ還される。
嗚呼、儂の身に意志が無ければ―――――。
「高名なる魔族どももこの程度か」
愚かにも、ワシに向かってくる魔物達。
そこは、魔界。
地上や天界、冥界と異なる――魔の巣窟である。
「バエル、アマイモン、アバドン、アスモダイ……………まさかこの程度で魔王の器を名乗ろうとは」
アマイモンの下半身は既に吹き飛び、アスモダイの全身は砕き、アバドンの頭は潰していた。
だが、この蜘蛛蛙猫――バエルだけはワシにまだ抵抗していた。
「よそ者がこの私に傷を負わせるとは……………………何者かは存じぬがもはや生きては返さんぞ!!」
バエルの右腕が勢いよくしなる。
硬質な爪は、防御の姿勢をとっていたワシの腕を飛ばすには十分な威力だった。
「ぐっ」
「焦ったな? このまま細切れにしてやろう!」
腕を吹き飛ばしたのを皮切りに、ワシの肉体を切り刻んでいくバエル。
臓物が飛んでいったか、肉が散ったか、骨ごと断たれたか。
それすらもわからずにただ、その場で立ち尽くす。
ひとしきり暴れ、バエルの吐息が漏れだしていた。
「くっ、はぁ、はぁ……………まだ倒れんか……………………!!」
再生する皮膚に、さらに攻撃し続けるバエルの姿は、実に必死に見えた。
「魔王の器がたかが知れるな。このありさまでは、な」
ワシが言ってやると、バエルは背中から蜘蛛の脚に似たものを飛び出させる。
「ならば、お前の体を喰らい糧としてくれよう!」
バエルはなにやら、ワシを喰う気でいるらしい。
八本の脚を、ワシの周りを取り囲む。
バエルの技や魔術は全て見た。
もはや、たかが知れた状態となっていた。
「―――できるものならやってみろ」
その脚を、ワシは全て片手で薙いだ。
すると、脚の役割をなしていた、棒切れが地面をのたうち転がっていく。
怯んだ隙に、距離を詰めて拳を放つ。
何が起こったのか理解できない様子で、こいつは、この一撃を許していた。
身を砕きながら飛ばした血と、骨の感触だけが言葉の代わりにそれを伝えている。
「貴様………………!! このバエルの腹を抉るとは………これだけの力を持っているのなら、他の連中を消すことも容易かろうに何故…………!!」
解をくれてやった。
どうせ、傲りのたまう肉片に過ぎぬのだから。
「なに、ただの余興だ。ワシは甦りたてなのでな、準備運動にと行きやすくなったここへ向かったのだが………期待外れも良いところだ」
貫いた腹に突き立てた拳を、上へ上げゆっくりと身を裂いてやった。
苦悶の表情を浮かべていたが、興味が無くなったのでどうでも良い。
「魔王の称号も安っぽいものだな。ワシが生まれた時には既に存在していたらしいが、この程度とは笑わせてくれる。なんてざまだ」
背中に生えた、昆虫のそれに近い羽根を揺らし、気絶しているアバドンの体を踏み抜き。
戦意を喪失している上半身だけのアマイモンを蹴り飛ばし。
全身を砕かれながらも、必死に再生せんと尽きている魔力を使うアスモダイの肉片を潰す。
散らかったゴミ山から進み、遠くでそびえる、悪魔属の魔王の城を目指した。
ゆっくりと歩き、ワシのリハビリに付き合える者を探すが、魔界中は静まり返っており――まるで葬式の中を進んでいるような気分にさせた。
「おいおい、我こそはというものはおらんのか。そら、ワシは逃げも隠れもせぬぞ?」
くるくると両腕を広げ、回りながら進んではみるが、誰も来ない。
魔王の城の手前にある、広い城下町へ辿り着いた時。
背後から、熱を感じた。
「――何?」
振り向いた瞬間、全身が灼熱の炎に包まれる。
皮膚が剥がれては、治っていくのを感じながら、目を開くと、眉目秀麗の悪魔が杖を構えているのに気づいた。
「―――ここはよそ者が荒らして良い場所ではない。帰りたまえよ」
「ほう、貴様はワシの準備運動に足る者なのかな」
ワシが笑んで返すと、悪魔は地面を蹴り奥へと距離をとった。
「これ以上暴れてみろ、魔界に混乱をもたらすのであれば私は容赦はしないよ」
悪魔が睨みつけると、悪魔の周囲に、氷の塊と炎の塊が出現し、周りをとりかこんでいった。
どうやら、威嚇のつもりらしい。
「ワシを前に警告するとはさぞ、名のある魔神なのだろう。その御名、ぜひ聞かせてもらいたいものだ」
質問してやると、悪魔は、神々しく十二枚の翼を背中から広げ、答える。
「我が名はダーク・ルシファー…………こう見えても、原初の魔界を治めていた者だ」
”ルシファー”。
その名は、かつて神々に反旗を翻した魔王の名を示す。
悪魔属の、長い歴史の創始者の一体だったか。
「大物、カリスマがやってくるとはアタリだな。では、その力を見せてもらおうか」
「それはそれはご挨拶だね、では、挨拶だけの関係を願いたいものだね」
ルシファーが杖を振りかざすと、杖の先端から火炎が迸り、同時に吹雪が身を襲った。
「炎と氷の魔術か…………魔術の中では王道だな」
言葉を返すと、ルシファーの顔にしわが寄った。
「君は、”奴”に似ている」
呟くと、ルシファーは全身に魔力を回しはじめ、巨大な氷塊と炎の塊が左右に浮かび上がった。
何らかの詠唱をしているようだったが、高速の為聞き取れることも無く――魔術がワシへ放たれた。
魔術を放つその瞬間、ほんの数秒だけ、赤と青の瞳が激しい光を灯していた。
「”己が身に宿りし深淵に溺れよ”!!」
魔術の名をはっきりと口にすると――ルシファーの体格の十倍はあろうかという溶岩と氷塊の鱗に身を包んだ、十本首の竜が杖の先端から現れた。
竜は炎と絶対零度の吹雪をまとい、漆黒の瘴気を、光り輝く口内から吐き出しながら体をうねらせ――ワシを飲み込まんとしていた。
ワシは直感で悟った。
これが、あやつの全力なのだ、と。
両腕を交差させ、防御の姿勢を取り、竜の一撃を受け止めた―――――――――――。
瞬間、血液ごと凍てつく感覚が全てに噛みついた。
竜が咀嚼するかのように、血管の中に血の氷の礫が、身を裂いていく。
次に、表面を炎が焦がし溶かしていく。
肉の形すら残さぬほどに、服の繊維が解れていく様に――あたかももとはそうあったかのように炎に消える。
視界はもはや失い、やがて意思も闇の中に消えていく。
ワシが最後に見た、ルシファーの体は、明星の如く光輝いて見えた――。
「くっ、久しぶりに無理しすぎたか」
ルシファーは魔術を放ち、”銀髪の怪物”の肉体を消滅させた後、杖に体をよりかからせた。
(かつての魔術を全力で再現してみたが………魔界の地面に穴が空かなかったということは、まさか奴は………………最後の一瞬まで持ちこたえていたという事か?)
膝から崩れ、漏れ出る吐息を、額からの粒粒を腕で拭うと共に抑える。
「やれやれ……魔界が焼け野原にならずに済んだだけ良しとしよう」
長く、乱れた髪を軽く後ろへ流し、息を整えた時。
ルシファーの背後に、気配が忍び寄った。
「今のは驚いたな。貴様の魔力はどうやら桁違いのようだ」
振り向く前に、蹴りをくれてやった。
まるでピンポン玉の様にはじけ飛んでいくルシファーのその滑稽さ。
「勢いはあった、だがいささか火力が足らなかったな」
一気に距離を詰め、走り寄るとルシファーは杖をワシの腹を貫いた。
岩の盛り上がった部分を背にし、折れているであろう肋骨の痛みを抑えて。
奴の口からは血が流れており、杖を刺しながらふらふらと立ちあがった。
「何故貴様は生きている………? 魔族でも、天界の者でもない様子だが……………」
「……………………ワシは、亡霊。あらゆるものの終着点にして”答え”だ」
言葉を聞く素振りも無く、ルシファーの顔からは余裕が消え失せていた。
嗚呼、ワシを恐れているのか。
「君が答えとするのならば、私は君を討ち、私の答えを刻んでやろう」
やってみるがいいさ。
ルシファーが杖を引き抜き、連続で突きを放つとワシは全てを躱し、膝蹴りをかました。
膝蹴りを杖で防御するが――意味など無かった。
杖は、膝蹴りによって真っ二つに折れてしまったのだから。
「馬鹿な!?」
直撃した蹴りに、体を折りたたませ、下げたルシファーの頭を掴むとワシはそのまま持ち上げた。
「貴様、この魔界に破壊をもたらして何が目的なんだ? 金か? それとも、魔界の破滅か?」
「いいだろう、とりこむ前に教えてやろう――」
「我が目的は、全世界の統一。全種族の更なる進化だ。不変の全てに終焉をもたらすのだよ……………その為には、全世界の破壊が必要不可欠でな」
「さ、貴様の魔力は魔王の器の中でも群を抜いているようだ。……………………いただくぞ、その肉体」
肉体をルシファーに覆いかぶさり、肉の全てでルシファーに絡みついていく。
抵抗はするが、空虚に腕だけを我が肉塊から飛び出させ―――体内で奴の意識が絶えるのを感じたのを最後に、元の形状へと戻した。
宝石の付いた、杖の先に付いた宝石越しにふと、己の体を覗いた。
それは、元来の姿に近い形状となっていた。
「……………良い、この調子なら―――」
これが、約四十年前の――魔界の記憶。
銀髪の怪物の、蹂躙の記憶である。
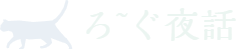


コメント