夕暮れ時。
陽の沈みゆく地平線へ向かって、一行は進み続けていた。
ソロムの感じ取った、ジェネルズの魔術の残り香を頼りに。
「ソロム、一体ジェネルズはどこに?」
快が後ろにつき、ソロムに視線を向ける。
ソロムは頭を掻いて言った。
「あいつも魔術が使える以上、痕跡が転々としてる。おまけに、この感じ……………」
「喰われたんだろ、宝石を」
快はソロムの問いに、若干顔を俯かせ無言で答える。
ソロムはその様子を見て、上着のポケットに手を入れ微笑んだ。
「なら仕方ない――取り戻そうぜ。俺達の抵抗の手段は、完全に奪われたわけじゃあないんだからな」
発言を聞いた、ソロムの背後を追うように歩いていた棕が、大声で返す。
「じゃあ、どうするってんのさ? あのびっくり鎧は無いし、かといって魔術もないんだろ? それに、追いかけることもできやしないし……………」
棕の隣で、翼をはためかせ追っていたアムドゥシアスは反応を示した。
「ワタクシは悪魔ですので、飛べはしますが……………棕と同時に皆さんを運ぶことはできませんしね」
「おい!」
棕の鉄拳が、アムドゥシアスの後頭部に振り下ろされた。
「君の体重に関して何もいってないのに……………」
煙のでる頭を抑え、アムドゥシアスは半目開きに言うが、棕は不機嫌そうにアムドゥシアスから顔を背ける。
「仲いいんだな、なっ、快」
ソロムが快の腕を肘でつつく。
快のその表情は、暗く――渋らせていた。
(…………ま、よく考えてみりゃ笑えないか)
ソロムにはただ、快の頭を撫でることしかできなかった。
何のやり取りも無く、広い道路を抜け、一行の歩みが未知の街へ着いた時。
「そうだ、ソロム。ユンガさんはどうした?」
快がやっと口を開いた。
「ユンガか、あいつはジェネルズと戦って――ぶっ飛ばされたよ。生きてはいるから大丈夫だと思うが、連絡はしばらく取れないだろうな」
真剣な眼差しを向けたソロムに、快は眼光を送る。
「何故、連れてこなかったんだ?」
「怪我がひどくてな、とても旅についていけるような状態じゃなかったからな、仕方ない事だ」
夕闇に顔の隠れかけた、快の姿はどこかソロムに不安げな印象を与えていた。
快はふと、人差し指にはめ込んだ指輪についた宝石を眺める。
ついていた宝石は、ダーカーズデビルノコンだった。
「ソロム、一つ質問いい?」
「おう、なんなりとどうぞ」
快は、宝石に映るソロムの姿を見ると――息をのみ、問いを投げかけた。
「この宝石……………一体”何”なんだ?」
「うちにも教えてくれ!」
棕が食い気味に、快の問いに割り込むとソロムは朗らかに答えて言う。
「そいつは、街で体験した通りの代物だ。魔王の器を一方的に滅ぼす程の力を備えた――危険な最終兵器。であると同時にそれを通して、色々な脅威度を報せ、念話を可能とするツールさ」
快は、声を低くさせた。
「じゃあ、あのジェネルズには最初からこれを使って倒せばよかったのか」
暗く顔をしかめたままに快が言うと、ソロムは周囲を見渡して言った。
「いや、賢明な判断だったと思うぞ。第一街中で大暴れするにしても、タイマンはともかく仲間が居るならその宝石の鎧は使わなかった方が良かった」
「なぁ、どんだけ危険なんだ? その鎧って」
棕は指輪を快の肩ごしに眺めていると、ソロムが表情を変えずに言い放つ。
「魔王の器……………簡単に言えば、大体自分のいる世界の全部を滅ぼせるぐらいの力を持ったやつを倒せるぐらい他の鎧とは別格の強化を受けられる。人間が装備できる中では、机上論では最強だろう」
ソロムが答えると、黙って棕の背後にいたアムドゥシアスが、ソロムを睨んだ。
「”机上論では”というと、何かデメリットでも?」
「あぁ、ダーカーズデビルノコンに関しては――これまでの触れた者の記憶だとか魔力量を全て吸収し記憶している。つまり、それだけ色々な触れた人物の感情にも触れるって事を意味している」
「その記憶・情報を引き出して、触れた最も強く多い感情と共に封じられている力を鎧や脅威度の測定という形で具現化させる。だが、他の宝石に比べてそんな膨大で強力な感情と魔力に人間風情が触れてみろ」
「―――理性も記憶も全部吹き飛ばして、殺戮と破壊の限りを尽くす魔人となってしまう」
ソロムの淡々と語る様は、周囲の仲間たちの固唾を誘い――沈黙をもたらしていた。
「そうだな、今考えられる最悪の事態とすれば――いや、止めておこう」
ソロムは、意味深に呟く。
呟く声を裏切るように――何かが一瞬、風と共に並んで進んでいた一行の列を割って通りすがった。
「なんだ? 鳥?」
周囲に鳥の様に思わせるその影は、虫の羽音を響かせていた。
「? まってください、快が居ません!」
アムドゥシアスが叫ぶと、棕は周りを見る。
「快!? どこだ!」
その一方で、ソロムは――アムドゥシアスが叫ぶ以前から上空の一点を見上げていた。
「あそこだ」
ソロムが上空に顎を突き出すような仕草を棕とアムドゥシアスに見せると、そこには、バッタの羽根を、丸く歪めた背中から生やした青年が居た。
青年が掴んでいたのは、快だった。
棕が上を見て、すぐに構えるが黙ってソロムは腕を棕の前に出し抑えていた。
抑えられた棕にはただ、じっとしている他になく。
「動くな。この少年は俺の一部を既に飲ませてる。俺を傷つければ、俺の一部。バッタが内臓を喰らいつくす」
「いきなり俺の仲間がご馳走になるとはどうも。で、要件はなんだ?―――バッタ男」
ソロムが煽り調子に罵ると、バッタ男はもがく快の口を抑えながら名乗りを上げた。
「我が名は魔王の器・アバドン。目的は一つ。だが貴様らに教えてやる道理、無し」
「………この少年に、指輪を使わせるのみ」
アバドンが目線を快にやる。
快は空中で暴れ続けていた。
(いきなり何故僕を狙う? 何故今指輪を使わせたがるんだ……狙っている事がわからない……)
快がひたすらに暴れ続けているとアバドンが快に囁く。
「その力を使い、ソロムを始末するなら今。お前は我々と手を組むと言った。ならば、やるべきことは、理解しているはず」
アバドンの囁きを聞き、快は指輪に一瞬目を落とした。
この力を使えば、確かにソロムも、ジェネルズも倒せるかもしれない。
しかし、それは仲間達への裏切りを意味していた。
迫られる選択を前に、快は―――。
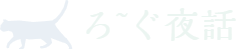


コメント