陰陽道。
それは、中国伝来の妖術を扱う者の道。
森羅万象は、陰と陽の要素によってできているという考えから発展した――東洋の占星魔術にして学問である。
西暦九百六十年代――平安の世。
かつて、陰陽道の極みに至ったという二人の陰陽師が居た。
陰陽占星術による、預言に長けた安倍晴明。
そして、陰陽呪術による防衛に長けた、蘆屋道満。
邪悪なる妖蔓延り、呪詛溢れる平安に、二人の陰陽師は互いに呪詛を祓い。
妖を退治し――あらゆる悪の怪異と遭遇し、それらを滅してきた。
時に、互いにその腕を確かめ合いながら。
腕の確かめ合いは妖術勝負で行われ、最強の陰陽師と謳われた、安倍晴明との闘いを蘆屋道満は何度も交わし、その様はいつしか平安京の華として有名になっていた。
数々の戦場を共にした盟友にして、強敵という存在感が両者の絆を確固たらしめる。
一方にちらつく、受け入れがたき影を除いては。
一 女法師 蘆屋道満
「道満法師殿! 道満法師殿はおりませぬか!」
人入り混じる、陰陽寮近くの平安京の道で、騒ぐ若者が居た。
若者は、焦げた衣服を身に纏っており、慌てふためいている様子だった。
若者が走っていると、足をもつれさせ地面に倒れる。
すると、偶然若者の脇を通っていた――飄々とした、人当たり良さげに見える女性が若者に手を差し伸べた。
「君が探している、道満法師はここに在り。……どうかしたかい?」
群青の髪色をした、女性は笑みをたたえ若者を支える。
その者こそ、道満法師こと、蘆屋道満だった。
道満法師に支えられ、若者が立ちあがると若者は息を切らして言う。
「妖が………妖が出たのです!!」
妖。
それは、平安時代に出没した、魔物――妖怪である。
妖を祓うのは、優れた陰陽師の仕事であった。
「妖退治かい? それなら、アキに頼れば良いのではないかな?」
「アキ……?」
若者が首を傾げると、道満法師は微笑んで返す。
「アキ、安倍晴明。話は聞いたことあるかい? 私より優れた妖力を備え、都では役小角の再来とまで謳われた――私の年下の友だよ」
道満法師が語る。
その表情は、若者にはどこか陰りがあるように見えていた。
若者は、首を横に振り、強く答えた。
「安倍晴明殿では、駄目なのです! あれはあなたにしか、頼めないし対処のしようがないことなのです!」
道満法師が目を丸くすると、周囲を見渡し、頷く。
「……ふむ、よろしい。急ぎの様子なんで、まずは仕事場へ向かおうか。」
道満法師は若者に目を合わせ、そう言った。
若者が、背後を指さす。
「奴は、播磨に居ます………!」
「なんと、播磨………か」
若者の言葉に、道満法師の笑みが崩れだしていった。
その額に、汗が滴ると若者は言う。
「奴は……凄まじい妖力を持っております。名を………」
「葛葉 焔總 と」
道満法師は、焦る若者と共に播磨へ向かった。
懐に忍ばせた、紙を指先で念じながら。
播磨。
そこは、平安京に隣接する地。
蘆屋道満の、故郷の国。
そして――大地震が起こった場所でもあった。
若者と共に道満法師が牛車に揺られていると、道満法師は突然声を上げる。
「止まれ!」
大声に驚いた牛車の仕丁は、思わず尻もちをついた。
仕丁が尻もちをつき、牛車を半ば強制的に止められると仕丁は後ろを振り向く。
向いた先は、道満法師。
「一体、どうしたのですか」
仕丁が困り顔で訊ねると、道満法師は牛車を降り、仕丁に言葉を返す。
「妖の気配を感じたので、ここから先、君らは通らない方がいい」
「法師殿、退治してくださるのですね」
牛車に置いて行かれた若者が、道満法師に視線を向けた。
その瞳は、信頼が込められていた。
道満法師は、その瞳を受け取り微笑む。
「ここからは、陰陽の世界。浮世を安泰へ導く事こそ、我ら陰陽師の務めってね。仕丁さん、若者を安全なところへ」
道満法師は、にこやかに若者と仕丁へ会釈を送ると、気配を辿る。
気配を辿っていくと、ただならぬ威圧が――道満法師の身を襲うようになっていった。
威圧は、道満法師の見知った者の放つそれと酷似していた。
(この妖気……安倍晴明のものか? いや、あいつは今越前へ居るはず。ならば、これほどの妖力を感じさせる妖気は一体……)
道満法師は、指先で念を込めていた数枚の紙を飛ばす。
紙が風に捲かれ、宙を舞うと道満法師は九字を切り、瞼を力強く閉じた。
九字を切る手が震えるほどに、紙に念を強く送ると数枚の紙はやがて――空中を漂う、魔物の姿となっていった。
陰陽師の使い魔、『式神』である。
数体の式神を宙に漂わせ、道満法師は妖気の元へ駆け寄って行く。
町を離れ、辿り着いた先は――鳥居の構える、古めかしい寺。
鳥居に捲かれていたであろうしめ縄は、真っ二つに切られており、寺からは僧が居るとは思えぬほどの妖気が匂っていた。
(ここ、だな)
道満法師は鳥居をくぐり、寺の中へ入ろうとする。
だが、鳥居をくぐろうとした瞬間、道満法師の体を炎が包み込んだ。
「ぐああああ!? なんだ!?」
炎は、激しく燃え盛り、道満法師は地面に体を伏せ身をよじる。
身をよじれども、体を何度も地面に擦り付けようとも炎は静まらず、かえって炎は燃え広がっていった。
道満法師が強く念じ、手を組む。
手は、仏の印の形を取らせていた。
「くっ……帝釈天よ、我が身に力を……オンインドラヤソワカ………!」
真言を唱えると、空は曇りだす。
炎が燃え広がり、鳥居付近が炎上し続ける中でもなお、真言を唱え続けた。
道満法師の衣服のほとんどが燃え尽きたところで、空から雨粒が降り注ぐ。
雨粒は、鳥居付近に集中し振り、炎を鎮火させていった。
しばらくすると、寺の奥から声が聞こえてきた。
「よおくやりなはった、ほんまごつい妖力やなぁ」
道満法師が声の聞こえる方を向くと、そこには――強大なる妖気の持ち主が、姿を現していた。
その者は、男とは思えぬ蠱惑的な色気を纏っていながら、女ともつかぬ刺すような殺意を漂わせている。
身に着けている服は、貴族のもの。
なにより、その者を妖たらしめているのは、頭に生えた、白狐の耳と背中から覗かせる複数の尻尾。
若者に怪我を負わせ、寺を荒らした者の正体と察するのは容易であった。
道満法師は立ちあがり、全ての式神を指先で操り、一直線にその者に向かって放った。
式神は、五尺程の毒蛇、毒蜘蛛、毒蛙の姿をしており、一気に飛び掛かる。
毒を吐き、身に纏いながら。
式神たちが、その者に触れる寸前。
式神たちは、突然苦しみだし、燃え尽きただの紙へ戻っていった。
道満法師は、その様を見て固唾を飲み、その者を睨んだ。
「……貴様が、葛葉焔總だな?」
道満法師が構え、九字を切る体制になるとその者は牙を覗かせ笑った。
「せやねぇ、そこまで知ってもうたんならしゃあないわぁ」
葛葉焔總は、人差し指と中指を揃えて構えると、寺の建造物全体が揺れだす。
揺れだしたのも束の間、寺に破裂音が響き渡り、寺の柱が宙を舞った。
「ほな、聞き返すけど……あんさんが、蘆屋道満で間違いあらへんのよね?」
寺の柱の先端が道満法師の前に向けられる。
道満法師は、冷静に答えた。
「そうだ、だったらどうした人外の者よ」
言葉を返した刹那。
寺の柱が、道満法師の腹を貫く。
背中へその先端が突き出し、道満法師自身が気が付いたころには、口許から血があふれ出ていた。
「……この蘆屋道満が……?! 貴様、もはや赦しを乞う等無駄と知れ!!」
道満法師が妖しげな笑みを浮かばせ続ける葛葉焔總を前に、真言を唱え始める。
足元は、既に崩れかかりながら。
「オン・マカラキャ・ソワカ…………大黒天よ!!」
道満法師が大きく唱えると、道満法師の体に凄まじき黄金と白銀の気が宿り、膨張を起こす。
膨張した気は、光線となって葛葉焔總へぶつけられていった。
「全く、高名な陰陽師でも神仏の力に頼らんとなんもできへんのかぁ。失望や」
葛葉焔總が軽く袖を振り上げると、光線は――瞬く間に消滅した。
目を疑った様子の道満法師を見て、葛葉焔總は口許を袖に隠し嗤う。
「殺しはせぇへんよ。ただ――安倍晴明が来るまでは」
「ふざけるな、安倍晴明と貴様に何の用がある!! 何故人々を襲う!」
道満法師の問いに、葛葉焔總はゆっくりと法師の元へ歩み寄り答えた。
道満法師の顎を、撫で。
「あいつとは、腹違いの兄弟なんや」
「腹違いの兄弟………? 葛葉という姓……まさか貴様は!!」
葛葉。
その名は、かつて安倍晴明が語った母の名。
神の使いたる、白狐の名だった。
「せや、俺が兄ってところやなぁ……」
「莫迦な、葛葉は稲荷様の使いと聞く! 貴様のようなただの狐狸妖怪を子に持つ筈がないだろう!」
道満法師が怒鳴ると、葛葉焔總は笑って人差し指を構える。
すると道満法師を貫いた柱は引き抜かれ、道満法師の動きを縛り付けた。
「せやね、けど……もしも、安倍晴明が禁断の子だったとしたら?」
「禁断の、子?」
焔總が頷くと、道満法師の腹に染み出ていた血液は止まる。
「まず、俺の昔話と過去を見てもらおうか」
葛葉焔總が指を鳴らすと、道満法師の目の前に鏡が現れた。
鏡は、漆によって黒く塗りつぶされており、鏡としての機能は無いに等しいかに思われる。
が、黒く塗りつぶされた個所は輝き始め――映像を映し出していった。
映し出されたのは、とある森の風景だった――。
二 妖狐、悲恋にて
人間は、恐ろしく滅ぼすべき“悪”である。
それは、あらゆる地に息をする妖怪達の教え。
絶対に、守るべき道徳認識であった。
妖の一種である、妖狐とて例外では無く。
和泉の国、信太の森の里に住む妖狐葛葉は、里を築き上げた最強の妖として恐れられていた。
その里は、戦によって滅びた人間の村の跡地に、結界を張ったものである。
人間が、入る事の決してない幻の地。
里の妖怪達は、葛葉を筆頭に、特に人間に対して抱く嫌悪が顕著に表れていた。
「そろそろ、里を下りて食事といこうかの」
空ぶき屋根の屋敷で、人の姿を真似ている白狐は呟く。
「葛葉様、お気をつけて」
白狐の隣で、巨大な頭の老人のような妖が言った。
後に、ぬらりひょんと呼ばれる妖である。
「何、ちと小鳥を二、三羽ばかり喰ろうてくるだけじゃ。ああいうのは、新鮮なうちに喰うのに限るからの」
葛葉が屋敷の縁側を降りると、屋敷の奥から小さな影が飛び出す。
「母上、僕の分もお土産にくださいね」
姿を現したのは、葛葉に似た姿をした妖狐――幼き焔總である。
「うむ、それと、墓に供える我が夫の分も取ってこなくてはな」
葛葉が屋敷を出て、里の外へ走って行くのを、焔總は手を振って見届けた。
母が出かけたのを見届けると、焔總は目の前にいるぬらりひょんに言う。
「一緒に父上の墓へ行こ、今日のお参りしていないし」
「ですな、行きましょうぞ」
焔總は、ぬらりひょんを連れ、屋敷の裏手に回った。
屋敷の裏手は、小さな墓石が点々と立っている、墓場となっていた。
その中に、焔總の身の丈の三倍はあろうかという大きさの墓石がそびえたっている。
墓石には、『葛葉獅狼』という名が刻まれていた。
墓石の前で、焔總は目を瞑り手を合わせる。
(父上、おはようございます。どうか母上の怪我無く狩りが終わりますように)
葛葉獅狼は、焔總の父である。
焔總が念じていると、ぬらりひょんが語り掛けた。
「焔總様、獅狼様の話は何度も聞いていますな……?」
声色は、どこか憂うように。
「聞いている、“人間といつか仲良くできる日がやってくるだろう。だからその日を作るため俺はしばらく里を離れる事にする、成功した暁には、皆に酒を振るまおう”といって里に下りて、殺されたって」
焔總がぬらりひょんに目線を送ると、ぬらりひょんは俯く。
「焔總様は、どうお考えですかな。獅狼様は、とてもお優しい方でした。里に来た時は、外の国からの侵略者だと言って皆から里八分にされていましたが、天狐の血を引く妖狐だと聞いて掌返しをする皆を前にしてなお、微笑んで仕方の無い事だとわらったあの時の表情は――昨日の様に思い出せます」
俯く老獪なる顔は、潤んだ瞳を隠すかのようだった。
焔總は、ため息をつき答える。
「俺は、父上の様にはなれないよ。だって、父上はそのために死んだ。だから母上もこの里をずっと隠している。母上が今生きていて、里の長になっている以上俺は母上の意思を尊重するまでだよ」
紅色の瞳を輝かせ、焔總が屋敷に戻ろうとするとぬらりひょんは後ろ姿に再び話しかけた。
「では、焔總様ご自身の思いは? あなた様が里の長となったらどうするおつもりで」
ぬらりひょんの声に、焔總は振り向き睨んで返す。
すると、ぬらりひょんの体が縛り付けられ、宙に浮いた。
「名も無い妖風情が、くどいぞ。だがもし俺が里の長となったら、俺は容赦なく人間どもを滅ぼす。父を殺した罪過を、けがらわしい土気色の皮と畜生にも劣る悪臭の血肉全体で贖ってもらう」
言葉を返すと、ぬらりひょんの足はゆっくりと地面に降ろされていく。
その様子を見ると、焔總は鼻息を飛ばし屋敷へと戻って行った。
「……獅狼様、あなたの切実な願いは徒と消えるのでしょうか。拙僧はただただ、悲しく思います。せめて、葛葉様がお考えを改めればあるいは――」
ぬらりひょんの呟きは、苔一つ生えていない墓石の前で消えた。
時間が過ぎ、里には夜の帳が降りていた。
屋敷に空いた天井から覗く、朧月を大の字になって、焔總は見る。
「遅いし、お腹すいたなぁ。そこの、干した魚はもうないのか」
隣で、筆を走らせ巻物に今日の出来事を綴っていたぬらりひょんが笑う。
「もうみんな平らげましたでしょう。もう今宵は寝ませぬか?」
「にしても、あまりにも遅すぎるだろう」
九本の尻尾でぬらりひょんの頬を撫でつつ、焔總は屋敷の玄関口へ向かった。
玄関へ出て、すぐさま屋敷の隣にある川へ曲がると焔總は両手を組み念じる。
やがて、稲穂と月を映しだすばかりの川の水に、葛葉の姿が薄っすらと浮かび上がった。
葛葉の白い体には、赤い斑点が滴り落ちていた。
(母上の体に傷が!?)
焔總は川からすぐ離れ、里の結界の出口となる――森まで走って行く。
出口まで走ると、そこには既に弱った様子で口に鳥を咥え帰った葛葉の姿が在った。
「母上!」
力一杯に抱きしめる焔總に、葛葉は笑んで優しく焔總の背中を撫でる。
「大丈夫だ、ちと油断しただけ。人間に射られかけるなど、里の妖全員に知られたら笑われてしまうじゃろうな。さ、あやつに干してもらって寝ようぞ」
その言葉を聞いた焔總の顔に、涙が浮かぶ。
嗚咽を堪えた、牙しまう口に、力が入って行った。
(やはり、人間は……滅ぼすべきなんだ)
しかし、そう言った葛葉の表情には、迷いを孕んでいた。
月に照らされた、二匹の妖狐はやがて――静かに眠りについていった。
それからというもの、葛葉は何かに悩み唸る様子を見せる事が多くなった。
と、同時に、里の外へ出かける事も多くなっていった。
ある日それに感ずいた焔總は、訊ねる。
「母上、何に悩んでいるのです?」
答えは、焔總の予想通りのものだった。
「なんでもないぞよ。さぁ、遊んでおいで」
葛葉の優しい顔に、焔總は小首を傾げつつ言った。
「そうですか、でも、悩みがある様子なら俺でも言ってくださいね? 俺は仮にも長となる者ですので」
それだけ言って、焔總は屋敷の裏手へと消えていった。
(……あの男の瞳は、確かに夫に似ていた。けれど、今の焔總に告げるべきではないじゃろう。しかしだからといって関係を続けるのも――――)
あの男。
それは二か月前、森に狩人に射られた際に、体に貫かれた矢を引き抜き葛葉を助けた男。
名は安倍保名と教わった。
(もしも、このことを告げれば多くの妖の反感を買うじゃろう。でも、この気持ちに嘘は附けぬ。だが、わらわが妖と知ればきっと)
人と妖は、相いれない。
自分自身が分かっていた事。
されど、矛盾が巣食う心の処理を、葛葉はできずにいた。
その裏で、焔總は密かに気付いていた。
人間へ、ひそかに会いに行っている事を。
既に、妖術で自分の母の秘密を占っていたのだ。
決して、口に出すことは無くとも。
(……憎み切れない理由ができてしまった俺は、どうすればいい。ああ言ってしまった手前、あいつにすら相談できない。だが)
焔總が軽く指を揃え、念じる。
そして、自分の体を屋敷の屋根へと飛ばした。
日差しに当たり、焔總は思いに耽る。
(俺は、母の思いを尊重すると一度誓った。ならば、母の想い人を通じて、父の願いもあわよくば成就するなら――俺はただ、黙っていよう。それが、この里と母の為だろう)
焔總は、術を飛ばして屋根の上の小石を浮かばせながら、ため息をついた。
自分の中での、結論をただ呑み込んで。
そして焔總は、里の中で何も悟られぬようにふるまい過ごすようになった。
例え、母が帰らぬようになっても。
焔總は、度々母の様子を、川の水越しに見つめた。
そこには、複雑そうな顔を浮かべながらも、幸せそうに人間として過ごす葛葉の姿があった。
鮮やかな畳の上で、雅なる服を身に纏う姿。
その隣には、穏やかそうな青年が居る。
焔總は、川の上に雫が垂れるのを堪え、深呼吸した。
「……人間、お前達の一生など我々の十分の一にも満たないだろう、せいぜい泡沫の如き生を謳歌するがいいさ。その刹那の時で、母上の考えを改めさせてみよ」
威厳ある、人の上に立つ――上位種としての台詞を強く言い聞かせる。
誰にも聞こえぬ、川の上に映されたものへの台詞だった。
それからだった。
焔總が、里の長として振る舞うようになったのは。
母の姿を、見ぬようになったのも。
十五年の時が過ぎ、焔總の体はほぼ人間の青年と変わらない姿となっていた。
里の長として、焔總は昼には結界を張り直し、里中を回り妖たちの棲む家を周り様子を伺う生活を送る。
夜には遠い日の、母の姿を思い浮かべつつ床についていた。
その胸には、どこか淡い期待が漂う。
母は、必ず帰ってくる、と。
(……母上は、今どこにいるのだろうか)
三日月を、縁側から眺めていると、背後から慌ただしくなる足音が聞こえてきた。
「焔總様! 焔總様!! 夜分に失礼します! 焔總様はいらっしゃいますか!」
声の主は、里の住人の一匹――後に、白坊主と呼ばれる妖だった。
後ろを向く事無く、素っ気なさげに口に扇子を当て焔總は返す。
「えらい時間に来なはって仕事熱心やなぁ、そんで、どないしたんや、名無しの一匹」
皮肉交じりに言うと、白坊主は玄関前にひれ伏し、告げた。
「焔總様……葛葉様が、ついにこの国から消えました!」
告げられた言葉は、衝撃的なものだった。
焔總は笑って返す。
「なんや、そないなこと昔から知ってる。せやから、こうして長になったんやろ?」
「………失礼しました」
焔總の言葉を聞き、白坊主はほっとしたようで一度会釈し、立ち去る。
しばらく、間を置いて。
焔總は、白坊主の報告が気になり、瞼を閉じて念じる。
(思えば、久しぶりだな。こうして妖術を使うのは………)
念じると、瞼の裏に浮かんだのは母の姿ではなく。
一人の、男の姿だった。
(!? 馬鹿な、この妖術は身に宿る妖力を辿ってみるもののはず……まさか)
額の上に、汗が垂れる。
(まさか、こいつは………まさかまさかまさかまさか!!!)
何度念じようと、映しだされるのは、その男の姿だけだった。
それも、妖術を扱い――妖を祓っている様子の男の姿。
その光景に、とある考えと共に憤りが募っていく。
考えられるのは、たった一つの憎き考えだった。
(そうか、こいつは母上が生んだ、否、産まされた子に違いない。下劣な人間どもが、妖に対する秘密兵器として! そして――母上はこいつに!)
「おのれェ!!!」
十本の尾の毛先が逆立ち、焔總が怒鳴ると焔總の目の前の地面に亀裂が入る。
「父上……俺の考えは間違っていた。そして、あなたの考えも! ええい、こうしてはいられない! 人類も! あいつも! あいつを殺す程の妖力を以て……確実に放ってくれようぞ!!」
怒りがこだまに響きわたっていったのは――平安、承平の時。
続
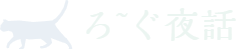


コメント