「銃なんか、握るな。刃なんて、むけるな」
そう言ってくれた人が居た。
もう、何年も前の話になるわけだが。
今日も今日とて、薄汚れた建物の影で、座ってふかす。
掃きだめのように、腐り荒み切ったこの町で。
そうしてくだらない考えをおともに、その辺の地べたに煙草の灰を落としていく。
この一時で、余計な過去だとかそういう――足手まといになるもんを捨てていくんだ。
なぁそこの坊主、ちょっくら話を聞いてくれや。
何、煙草はやれねぇが、チョコと、食いきれなかった弁当ぐらいなら持ってるからよ。
俺が“この世界”に入ったのは、丁度坊主よりも数個上、十五歳ぐらいのころだったかな。
故郷は、ジョンヴァエ州の町。
聞いた事がないだろ? だったら、見せてやりたいよ。
夜はトドみてぇなおっさん共と、瘦せこけたスケルトン女が着飾ってそいつらと毎日道路上の緑を増やしてるあの光景を。
緑といっても、割れたガラス瓶とジャンクフードの包み紙だが。
それが朝方になると、全部が照らされて、ぴかぴか光って眩しかった。
路上でたむろして、遊び呆けていたトドとスケルトンは、朝から昼間にかけて居なくなって、代わりにみすぼらしいミイラどもが物を乞う。
うけるよ、日の出る時間は寂しい灰色になって、夜は喧しいまでの乱痴気騒ぎ。
そんな町で、俺は酒場のバーテンの息子として生まれた。
おふくろは、優しいウェイトレス。
二人のなれそめは、夢を追い続ける親父の姿に惚れて、親父は美味しそうに酒を飲むおふくろの姿に惚れたのだという。
聞いていて恥ずかしくなるぐらいの、純情の両想いだった。
親父曰く、この町に居るのは自分のバーテンとしての“練習場”と“資金繰り”としての意味があるらしかった。
営業時間が終わると、夢に向かって、色んな酒の種類を覚えては、カクテルを自分で試飲しまくっては酔いつぶれている姿が見られる。
その様子がちょっと面白くて、色々俺も悪戯代わりに適当な酒を混ぜては「新作のアイデアにどう?」なんていって飲ませてた。
けど、どんなに潰れちまっても決まって「おお、ありがとう。試してみる」とか言って無理に飲みまくって。
挙句、二日酔いに悩まされていた。
その時は流石に、悪いと思っていたさ。
あれ以来親父の後ろで、グラスを磨く毎日。
けど、不思議となんだか応援したい気持ちも強くなっていた。
いつか、俺も親父の夢の手伝いをするんだ。
そんな風に、考えていた矢先。
――爆音が、全部を吹き飛ばしていった。
事が起きたのは、俺が寝ていた時だったかな。
目を擦りながら、おふくろに手を引かれて店の外に連れ出されて、走っている内に靴になんかの破片が挟まって、痛かったのを覚えている。
ただ、覚えている事は―――その手を引いていたおふくろの足も、そのうち止まってしまったってこと。
その後、俺が後ろを向いた時気づいたんだ。
親父の店が、俺らの店が、瓦礫と炎に消えちまったことを。
周りを見たら、全部がいつもと違っていた。
地べたで寝て居る赤茶けた肌のおっさんは、頭に穴が空いていたし、やせっぽちのご老人は背中を上にして、TVでみた映画に出ていた虎のじゅうたんみたいな顔をしてやがる。
その様子と、突然横で倒れたおふくろの体を見て気付いたんだ。
皆、“死んだ”ってことを。
上を見上げたら、鳥みたいな鉄くずが、鳥の真似して列になって空を飛んでいた。
そいつが遠くで糞をまき散らすと、当たったところから一気に町が崩れていく。
みんな、泣き叫んでいたよ。
正面も後ろも、向けば普段見ないような顔ぶれが、ヘドロを被ったみたいなすすと土埃と涙でどろどろになった顔で必死になって走り去っていく。
それらを、一人残らず、撃ちぬいていくのは、後ろから迫りくる――ヘルメットを深々と被って、銃を構えた茶色い服の野郎どもだった。
意味の解らない言葉を、皆叫んで、近所の知らない顔、体に風穴を開けていくその様は、小さい俺にとって怖かった。
俺も倒れて動かなくなったおふくろを置いて。
親父の店を置いて、町の人らにもみくちゃにされながら走った。
その後からだった、俺にとっての地獄が始まったのは。
戦争が激しくなって、俺は隣町まで逃げ延びた。
毎日、スリでもやらなきゃ腹が減ってたまらなくて。
なりふり構ってられなかった。
おふくろのよく作ってくれた、シチューの味が恋しくて泣きながら、バンパーがぶっ壊された車の陰で貪ったトマトの味は今でも忘れられない。
逃げ延びた町は、港町だった。
潮風がよく吹いていて、市場には旨そうな魚が並んで、それに釣られたみたいに人だかりが良くできて。
俺は、スリに行くときそこを狙っていた。
しばらくはそうして過ごしていたが、逃げ延びた町もいよいよ貧しくなってある張り紙が貼られるようになった。
『徴兵』の紙だ。
胸の肋骨が浮き出て、全身が枯れ枝みたいになった頃、俺は、その張り紙を手にして――馬鹿な決断をしちまった。
“国の兵士になって、飯を腹いっぱい食うんだ” って。
張り紙には、丁度当時の俺が年齢に組み込まれていた。
そして、俺は国の首都まで足を引きずって歩いて。
くそくらえな上官、先輩風を吹かして地獄へ堕ちた二等兵とその連れの指導を受けて、俺は銃を握るようになった。
あの二等兵は、特にお人好しで、お節介だったことはよく覚えてる。
俺に「銃なんか握るな」とか言って、志願を最期までさせようとしなかった。
最期もお節介なもんで、俺と一緒に配属された隊の中で、戦いの待っ最中だってのにスラムになった町のくりくり坊主を庇って、俺を残していっちまったんだ。
皮肉なもんだよな、戦争を憎んでいたはずなのに、生きる為に戦争してて。
そして、誰かに傷つけられた俺は、誰かを傷つけてる。
なぁ、坊主。
俺の腹を見てみろ、もうこんなに赤い、地獄行の印が付いちまってる。
チョコも、弁当もくれてやるから、どうか誰かに伝えてくれないか?
「俺達は争いたくて、争ってんじゃない。だから、憎しみ合うんじゃなくて、ただ、事が済むまで逃げ延びてくれ。俺達と同じように、銃を握らないでくれ」って。
それと、弁当もお前の仲間に分けてやってくれ。
こんな銃、あの土埃に埋もれて、消えてなくなって欲しいもんだな。
さ、煙草は無くなったし、もう思い残すことはなくなった。
――今度は、お前らがどうするかを、考えな。
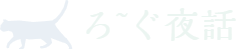


コメント