誰かが言っていた。
ボクは、失敗作だと。
思い出したくもない、憎い顔は忘れられなくて。
それでも、ボクは縋っていた。
守護神だと、謳われていたものに。
そして自分の、憧れていた存在達に。
もがいて、あがいて。
戦い続けた。
けれど――その果てにあったのはただの裏切り。
姿を追っていたものが、形の無い物だったのだ。
ボクの体が、最初にバラバラに砕け散った時、それを感じていた。
あの時、今思えばボクは狂っていたのだろう。
望んでいたものが、必ず手に入るはずもないのに。
――それから、ボクは何もかもがどうでもよくなった。
さて、回想に耽るのもここまでとしよう。
これからのボクは、あいつの失敗作でもない。
ただの、破壊者だ。
例え、残酷な世界だったとしてもボクはボクであり続けるのみ。
あいつが倒れて、また奴が生き残る。
でも、もしあそこで奴が倒れてくれたら、今度はかつてと状況が全く違う。
また、やってやるとも。
都合のいい体も、手に入れた事だし。
――さて、破壊を愉しもうじゃないか。
――――
グループホームの、台所奥に置かれた食卓。
その席に座って行くのは、子供達。
「さ、喰うぞ~」
鍋を両手に持ち、食卓の中心にギルバルトがそれを置くと、蓋を取った。
と同時に、周囲は温かな湯気で満たされる。
湯気がひとしきり子供たちの視界を遮ると、鍋の中身が露わになった。
快が一度に集う子供たちに割って入り、その中を思わず、覗き込む。
食欲をそそる香りと共に、人参、ブロッコリー、ジャガイモ……色とりどりの具材が、目の前で迎えるかのように出揃い鮮やかに黄白色に包まれ煮立っていた。
「ほらほら、そうがっつきなさんなって。ちゃんと快のもあるから……よっと」
ギルバルトが手袋を外し、食卓の中心にある椅子に座ると、子供たちは合掌した。
人数分の食器の置かれた食卓を囲み、子供たちは声を合わせる。
「いただきまーす!」
子供たちの声が響いた後、ギルバルトが軽く頷き、鍋に入れていたオタマを握った。
オタマを握り、ギルバルトは各々の前に置かれた真っ白な皿に中身をよそっていくと、ちはが我先にと皿を両手で持ち差し出す。
その様を見て、快の隣に座り佇んでいた華弥子が笑んだ。
「あらあら、ちはちゃん。焦っちゃだめよ。ギルちゃん困るから」
華弥子の言葉で、ちはは頬を膨らませて静かに席に座る。
椅子の軋む音を聞き、春斗は噴出しかねない笑いをこらえていた。
快の隣で、華弥子が自分の頬を抑え、申し訳なさげに擦る。
「ごめんなさいね、私料理ができなくって……」
華弥子が快に向かって言うと、スプーンの先を口へ持っていた春斗が便乗するかのように言った。
「つい一か月前、台所に立ったら大惨事でしたもんね。金属が焦げた臭いはするわ、何かと思えば爆発音なのか何かを焼いているのか判別がつかない音が鳴ってたですもん」
春斗が言うと、皿に盛られたシチューを頬張っていた大司がため息をついて返す。
「はぁ、あれはこわかったよ。オーナーさんがかいだしにいってたときだっけ」
ギルバルトが全員分配膳し終え、大司の発言にスプーンを口に運びつつ苦笑を浮かべた。
一瞬、鋭い歯を見せて。
「あはは、ありゃ笑えなかった。帰ってきたら春斗は大司の隣で鼻をぴくぴくさせてたしちははバケツを被って洗面器一杯に水を汲んで、華弥子の顔は煤だらけのちぢれ髪乱れ髪。びっくりしないほうが無理だったよ」
ギルバルトの笑いに、いつの間にか快が向くころにはただ華弥子は頬を染めつつ、黙ってシチューを味わっていた。
快は、皆がシチューを三口ほど食べているのを見て、快はシチューを口にする。
舌の上に広がる温かく、うまみの詰まったスープの味。
初めての、歯の下で咀嚼する――根菜の食感。
咀嚼したものを、喉の下へと送る感覚。
全てが、快にとって新鮮なもの。
であり――涙が、あふれ出るものだった。
「? どうしたの?」
華弥子が声をかけると、それが一気に流れ、快の匙が震えながら進んでいく。
「いや……なんでも……ないっ……です……!」
快が涙ながらに食事を進めている様子を見て、他の四人は目を丸くしていた。
快の空になった皿を見ると、ギルバルトがオタマを手に取り鍋の残りをよそう。
「苦労してきたんだな、たくさん、たくさん……喰いな」
そう言うと、華弥子、大司、ちはが頷いた。
「今日は、歓迎会代わりにあたしが我慢するから、一杯食べて。痩せっぽちで、見てられないしね」
「ぼくも」
大司とちは、華弥子は、快の食事を見守る。
快は、周りを見て、またしても涙を流さずにはいられなかった。
「皆――ありがとう、ありがとう……美味しいよ、凄く……」
勝ち取った“食事”を噛み締め、快はただ感謝と共に――匙を進めて行った。
鍋が空になり、満腹に酔いしれた黄昏時に、ようやくの平和を実感して。
戦いからの、解放を享受したのであった。
ただ一つ、黒衣の戦友の影を脳裏に落として。
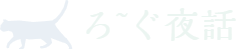


コメント