魔界。
そこは、異形の怪物――――魔族が蔓延る異世界。
かつて英雄を前に敗れ、倒れた者。
神々に挑戦し、反旗を翻さんとした者。
第二の生を享受する、彼らの安寧の地にして、戦場。
同時に、子を養う場でもある。
これは、起こり得た未来の話。
悪魔属の支配者にして、全魔族の帝王とまで呼ばれた、栄光の魔王が居た。
禁忌の神話に記される、魔神。
広大な魔界の、三分の一に渡るプエルラ地方、その地域一帯を統べていた大魔王。
プエルラ・テネブリス――――テネブリス家第65代目当主にして、“禁忌”の21番に記された者である。
彼女は反転浸食病に侵されながらも、それすら呑み込み、我が力とした(孤独なる魔王)
若き日には、禁忌と呼ばれる者との相対を果たしながらも生還し、地上界の危機を救う一手ももたらした。
魔界では、異例の存在。
悪魔属の魔王の器ルシファー、テュポーンすらも彼女に敵わないという。
そんな彼女を、打倒す存在が現れようとは、誰が思っただろうか。
――――神話と、歴史の狭間を、作り出した者が。
事の発端は、ただの噂だった。
“やがて、魔王の絶対王政”が途絶えるという、魔族間での噂である。
プエルラ地方、テネブリス城の構えられた城下町で発せられた噂は、山、川を越えてあらゆる場所で流行り病のように伝染していく。
魔界は、地上界と比較し魔力、実力至上の思想が強かった。
実際に強く無ければ、声を上げる事も許されない。
プエルラが魔王となり、外交によって異種族間での境界も無くなり、それは確かな“種族間”での差別を無くす事に成功した。
山の一部に転移魔術による移動が可能なトンネルを設け、種族による結界魔術の使用を禁止される、通交税の一律化、語学の強化……全て、他種族との融和と平和的な統治に役立っていた。
魔術に頼った生活システム、そして地上界の生物以上に強力な超生物である魔族にとっての権力は、戦闘能力と、豊かな想像を具現化できる魔力が全て。
当然だが全て、地上界とは、異なった価値観を有していた。
故に、弱者に人権ともいうべき権利はなく、声を上げる事は一切許されない。
国民としての基準は、総合脅威度Dからというもの。
それ以外は奴隷とされるが、総合脅威度が地上界における人間――――19世紀以降の種族と同程度であれば、どの種族からも爪弾きにされ、放浪し果てるしかない。
血統と種族の垣根は壊した。
だが、染み付いた、己の内でも壊せなかった弱者と強者の格差だけは、大魔王は壊せずに居たのだ。
そんな格差を、壊して欲しいと切に願った、誰かの呟きが噂として広まったのだろう。
城内を警備するリザードマン達から噂を耳にした、ユンガ・テネブリスは城の階段を上がりながら、そう楽観的に捉えていた――――。
もしも、姉の支配が崩れるならば。
僕は、全てを投げ打ってでもこの地を守る。
それが国の民の声だったとしても。
口には出せぬ思いを胸に、血のような紅の絨毯と、地上界のゴシック文化にある物に似た、踊り場の時計の前を通り過ぎる。
時計の針は、ただ|機械《からくり》として進む時を刻み続けていた。
魔王プエルラテネブリス。
その年齢は今や、誰も知る事は出来ない。
10万歳――人間で言うなれば、上級魔族の中では10代前半に当たる年齢でこの座に着き、大英雄との戦に出たと、魔界の歴史書では記されている。
しかし、近年では魔王の座の実質的な独占の正当化、神格化を兼ねた捏造だと見られていた。
長髪に、片目の漆黒に限りなく近く、遠く、白銀にも似ているが遠い色の眼と、その顔の上から胸元にまで刻まれた同色の傷が、かつての英雄との戦いを証明する傷だという。
魔族は外見の衰えがある一定の期間で止まり、年齢を一切感じさせないで永遠と成長し続ける事ができる。
プエルラの場合は、その恩恵が顕著に表れており、人型で居る事も相まって、少女性の愛らしさと豊満なる美を兼ね備えた美貌を持っていた。
それが、徒となって今も尚、捏造の意見を強めているのは気にも止めていなかった。
自身の捏造の噂、王政の崩壊について。
全て、プエルラにとってどうでも良かった。
王政の崩壊の噂、それが弱肉強食は世の常。
自分らが強くなれば万事解決。
――――強くならないのならば、生きる価値すらない。
それは身を以て、かつて知った世界の絶対常識。
我が道を、邪魔するのなら力を示して見せろ。
余はその全てを薙ぎ払ってみせよう。
それが、魔王である。
胸の内に思いを秘めつつ、舌を動かす。
亜竜属、亜人属、妖精属、魔獣属、吸血鬼属、幽属との会談で――――この日は、貴族への必要納税額について語っていた。
その中で、圧倒的な主導権を握っているのは言わずもがな。
惧れと、妬みを買われているとは知らずに。
第一章 荒野の子
吹きすさぶ嵐。
雨粒は骨穿つ弾丸、荒れ狂う風は肉引き裂く真空。
大地に隆起するのは、悪鬼の牙を思わせる紫の丘、それらを陣獲るのは、毒々し気な桃色と水色の枯草達。
地上界では、ありえない程過酷な環境、生物が居るとは信じがたいそこに、“彼ら”は居た。
「よしよし……ボグエベ、お腹、空いたろ」
角の折れた、雑種の魔族。
青白い肌に、人に似た外見は、名家の血筋であった事が伺える。
彼が抱えるのは、魔獣属の魔族。
毛の一切ない犬のような外見に、寸胴から伸びた6本の足に、虫の脚を思わせる尻尾の付いた者だった。
身体は骨張り、口は乾ききっているボグエベに、雑種――――バスタルドは頭を撫でて、嵐の荒野を突き進んでいく。
魔界の荒野に振る雨粒は鋭い毒のトゲ――――というのも、魔界の荒野に振る雨は地上界や天界のそれとは異なっている。
月から送られてくる、雲に含まれた、様々な元素の入り混じった魔力が時折、重力に任せて降り注ぐのだ。
再生能力の高い、魔族すら通交を恐れる荒野の名は、“魔神の通り道”と呼ばれている。
バスタルドにとって、そこは衣食住の整った唯一の安全な住処でもあり、戦場だった。
言葉を話せない異形の友を抱え、突き進んでいくその背中に付いてくるのは、三つ目の魔族。
彼もまた、バスタルドの友とする存在、アルゾス。
痩せ細った体を、引きずってアルゾスは二歩分進んだ友に言う。
「なぁ……ここで、いいだろ……? 断食は、俺も慣れてるからさ……」
「何を言っている、皆お腹空いてるから進むしかないんだろう? 草も食べられないし、ここ最近は他の奴らが一匹も見当たらないし」
「でも、国じゃあ確か他種族の殺害は罰せられるんだろ? どこに出るかもわかんないのに……」
「捕食目的なら別だと兄から聞いた事がある。ほら、遠くに森が見えて来た」
バスタルドが前方を指さす。
前方には、黒々と葉が生い茂る森林が有り、それはアルゾスらに希望を与えると同時に、不安感も伴わせていく。
森林には、他の自分らよりも強力な魔族が居るだろうという妄想が、アルゾスを震えさせてやまなかった。
アルゾスの様子を顧みる事無く、バスタルドはボグエベを撫でながら進む。
三体が森に入ると、とげとげしい茂みが彼らを迎え入れていった。
踏みしめるだけで越えられそうな茂みを、バスタルドは両手が塞がっている事もあり、こけかけながら、足元で地面を探り通って行く。
そうして、森の奥深くへ行くと、ボグエベが上を見上げる。
そこで笑んでいる、圧倒的な絶望に気付いたのはボグエベが最初。
次に、頭上から頭皮を焼くような魔力を辿り、存在に感づく二体。
三体は確信する。
“今、上を見上げれば死ぬ”と。
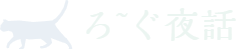


コメント