吸血鬼属は、人間への擬態に優れた一族である。
故に、かつての人間との戦争では財力などの水面下の戦力を奪うことによって魔王に貢献していた。
「愛おしくも哀しき同胞達よ__反撃の刻だ」
逢魔が時を示す空を、黒煙の如き軍勢で覆っていく吸血鬼達。
そこは、人間界、西部に位置する孤島の村。
一〇体の吸血鬼達は、ブロード王国を偵察した後遠方……王国本土から西へ一〇kmにある領土へ攻め入っていた。
孤島もまたその仇敵の支配する地の一端だった。
「全員、擬態は済んだか? では行こうか」
羽を広げ飛行する軍勢の先頭に立っていたドラキュラが、擬態を済ませた仲間へ声をかける。
すると、仲間の一体が地面に降り立った。
それを合図に、吸血鬼属は村近くの森林へ飛び込み、自身らの衣服を木々の枝で切り刻んでいった。
そして、吸血鬼属達は森を歩いて村へ向かう。
その姿は、何者かの襲撃を受けた貴族のそれだった。
「わざわざ、あの国の近辺の町の服職人を脅して手に入れただけの事はあって、装飾が豪華で傷つくのが勿体ないな」
吸血鬼属の一体が呟く。
「なら、あやつを徹底的に滅ぼしたのち存分に着させてやる。その服をブロード王国が滅亡した証としてくれるわ」
部下の言葉に、ドラキュラは鼻で笑いながら返した。
吸血鬼一行が歩いていると、村の門が見えてきた。
その村の門は固く閉ざされており、門の柱には松明が灯されていた。
「いかがいたしましょう、ダーク・ドラキュラ様」
背の低い吸血鬼が、機嫌を伺うかの様にドラキュラに問うと、ドラキュラは爪を立てる。
「ああ、丁度いいな、こうするまでよ」
ドラキュラが爪を軽く横に振るうと、門は三枚おろしに切れ始め、門が形を歪ませていくと共に、松明の炎がその場から崩れていった。
炎はやがて燃え広がって行き、門だったがれきを火の山へと変えていく。
燃えてからしばらくするとドラキュラは声を上げる。
「ブロード王国の者だ!! 襲撃されている!!」
ゆらゆら揺れる炎の先に見える村には、民家のほか兵舎が見え、王国兵が駐留しているのは明らかだった。
吸血鬼の一体をドラキュラが睨むと、その吸血鬼は炎をかいくぐり兵舎へ向かっていった。
兵舎の中へ入っていくと、そこには藁のベッドが複数乱雑に敷き詰められており、ベッドには兵士たちが鎧を着たまま寝そべっていた。
「起きろ!! 門が倒壊して火事が起こってるぞ!!」
吸血鬼が入口付近のベッドに寝ていた兵士の体を揺さぶった。
「寝かせてくれ……頼む……もう疲れてんだ……」
吸血鬼の方を向いたその顔には隈が浮かんでいた。
「何を言っている! 火事だぞ!?」
いよいよ煙が兵舎の方へ向かいはじめたところで、揺さぶられた兵士は飛び起きた。
「なんだと……あぁもう、俺らの国はいくつの国の恨みを買えば気が済むんだ……」
兵士はそのまま、足を引きずらせながら門の方へ向かった。
すると、兵士は慌てた様子で兵舎のもとへ戻ってきた。
「ちょ、みんな起きてくれ!! 大変だ! 寝てる場合じゃねぇ!」
「だから言ったでしょうに!」
貴族に扮した吸血鬼と、兵士は残る兵士を全員強制的に起こし、兵達は門の元へ向かっていった。
すると、火は既に消し止められていた。
門の形を成していたガレキを、残して。
「どういう事だ……? 門が崩されている……だと!?」
兵士の中でも、マントを羽織った兵士が声を絞り出すかのように言う。
兵士たちがあっけに取られていると、門の先の闇に紛れ貴族と思しき格好の男女の集団が現れた。
しかし、その服は切り刻まれていた。
「!? ブロード王国の……上級貴族様!?」
おぼつかない様子で、兵士たちは目の前に現れた貴族を前に跪いた。
それを見た、貴族の先頭に立つ、特に見た目麗しき貴族は必死げな表情を浮かべ口を開いた。
「はぁ……はぁ……儀礼は良い、それよりも……この門だ!」
「火は、我々がなんとか打ち消したが、誰がやったと思う?」
先頭に立っている貴族が口許を歪ませながら怒鳴るように兵士達に問う。
兵士たちは黙っていた。
しかし、続け様に貴族の男は畳みかける。
「__……ブロード王国本土の連中だ」
「!? 今、なんと……!?」
兵士たちは耳を疑い、その場が一瞬で凍り付いた。
「ここは辺境の村だ。しかし、お前たちの人種はブロード王国の人種とは大きく異なっている……即ち、ブロード王国にとって、不都合な文化が残っていたから滅ぼそうとしたのだろう」
兵士の一人が立ちあがり、声を荒げた。
「何を言っているのですか!! 我らが王は、何の隔たりなく我らを愛しておられるお方だ!!」
「おい!ペルシ! 落ち着け!卿の御前だぞ!」
マントを付けた兵士が、ペルシと呼んだ傷だらけの鎧の兵士の肩を掴み、声をかけた。
その様子に、男は淡々と語った。
「実際に、先ほどまでブロード王国の魔術師がこちらに炎を放っていたのを見たが、私は一瞬目を疑ったよ……」
貴族の男は、懐から杖を出した。
「これが、その魔術師の使っていた杖だ。なんとか奪ってやったわ」
その杖には、魔術の名が柄に刻まれており、先端には緑色の宝玉がはめ込まれていた。
杖を見せ終えると、男は杖を兵士たちの前に放り投げた。
マントの兵士は、それを拾い上げ、手に取りまじまじと見つめた。
「……これはまさしく、ブロード王国専属魔術師に送られる魔法杖……」
そう呟く、マントの兵士からぽつり、ぽつりと雫が零れる。
村人達が寝静まった夜に、響く嗚咽。
「なんで……なんで……」
「言いにくいが、お前たちの姿を見てみろ。王国の城下町に住まう人々と、己が身を」
兵士たちは、兜を脱ぎ兜に反射される自分たちの姿を見た。
城下町に住まう人々とは違い、淡い橙色ではなく小麦色に焼けた肌。
赤でも、黄色でもない、漆黒の髪色。
陶器でできているかのような鼻をもつわけでもなく、団子のような鼻。
全てにおいて、城下町に居る人々とかけ離れた外見__
「ほら、外見だけでも思い当たる節はあるだろう?」
「だとしたらなんだ!! 俺らが!! あいつらに敵う筈がないだろう!! 逃げるしか……ないじゃないか」
マントの兵士が涙ながらに男に訴えるかのように言う。
すると、男は微笑む。
「……だろう、しかし私はあの国に愛想が尽きたのだ。民を愛すると言っておきながら、このような仕打ちをするような国、強国とはいえ反吐が出るわ」
男が、兵士に歩み寄り始めると、後ろの貴族たちも目を妖しく輝かせながら音もなく寄り始める。
「そこで、だ_」
そして空は、やがて一面黒で染まっていたものを、金色の月で照らしだした。
「私に、協力すると言えば王国に一矢、報いる事ができるだろう……いかがかな」
男の目は、黄金の月に照らされてか、兵士からは輝いて見えていた。
「……協力は惜しみませんが、どうやって?」
マントの兵士は戸惑う。
戸惑っている兵士に向かって、男は両腕を広げる。
「……まず、ここ近辺の別の貴族の居る城へ案内するのだ。夜明け前にな」
そう告げた後、後ろにいる貴族へ耳打ちし、村の兵舎へと耳打ちをした貴族たちは去って行った。
「わかりました。……ところで、なんと呼べば?」
マントの兵士が尋ねると、貴族の男は長い後ろ髪をなびかせ名乗る。
「私の名は、ドラキュラ……ある国の元王だよ」
金色が漆黒へと再び塗りつぶされていく空に、人ならざる者の名と、男たちの怒号が響いた。
もはや、この空が再び金色を見せる事は無い。
同時刻、魔界。
悪魔属魔王城には、魔獣の王と悪魔の王が相まみえていた。
「さて、談笑はここまでとして……プエルラよ、 お前に提案だ」
「……あの男を、自らの手で討ち取りたくないか?」
キマイラはプエルラに手を伸ばす。
「あの男……」
伸ばされた手を見つめた後、プエルラは俯き、拳を握った。
「どうだ? 悪い話ではあるまい。仲間も引き連れ既に計画は動いている、あとはお前の意思次第だ」
拳を作るプエルラを覗くキマイラのその瞳は、爛々と輝いていた。
「許さない、許せないよ」
絞り出された声には、激情が宿っているかのように深くくぐもっていた。
それを聞いたキマイラは確信した様子で微笑む。
「では、我々に協力すると?」
そう言ったその時には、キマイラの手にプエルラの小さな手が握られていた。
キマイラがプエルラの姿を、見るとその姿は、交戦時と同じ、灰色の魔力を体にまとわせていた。
「……なんだってやってやる。この身が朽ちようと、地獄の果てまであいつを追い詰めてくれる」
「素晴らしい返事だ。 その形相、まさに悪魔の神髄よな」
「魔獣に、悪魔の何たるかなんてわからないだろう」
「一本取られたな、クク。では、行こうか」
キマイラは翼を広げる。
「どこへ行く?」
プエルラが尋ねると、キマイラは間を置いて答えた。
「吸血鬼属の王の城だ。 そこの会議室を借り集合しているのでな、お前も連れて行こうと思ったのだが……どうする?」
プエルラはそれを聞き、後ろの階段へ足を動かした。
「少し待って」
振り向いてキマイラに言い残し、向かった先は寝室だった。
寝室の扉を開けた先にあるベッドの、その上には、ユンガが穏やかな寝息を立て眠っていた。
「ユンガ、しばらくだけお別れだ」
プエルラは、ユンガの元へ飛び込み、その傍らで横たわってユンガの前髪をかきあげた。
「……また、必ず戻ってくるから。……もう、一人にしないから」
ユンガの額に、プエルラの透明な唇が触れる。
「じゃあ、頼んだぞ」
プエルラはユンガを抱き寄せた後、ベッドから離れ、扉を開けた。
扉を開け、プエルラがふと後ろへ向くと、穏やかな日常の一端が眼に映った。
プエルラは、優しくも、重々しく_扉によってゆっくりと視界から遮られていくそれらに別れを告げた。
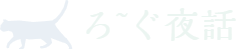



コメント