破壊され目の前に散らばった短剣と、鎧。
硝子の破片に映る燃え尽きた街並みが、それまで生きていた世界の全て――それまで生きていた時代が、終わりを告げたことを報せる。
ガレキの山に潰れるは、その時代の象徴。
民に愛され、崇拝された、英雄の末路である。
僕が山から飛び出した手を握った時には、既に冷たくなっており、手を離すと力なく垂れていった。
彼の功績は、僕だけでなく誰もが知っていた。
彼は幼き頃より、騎士に憧れを抱き村を飛び出し、かつて小国だった元サドネス公国の騎士団に入ったという。
そして、地上にはびこる名だたる魔族を討ち、敵国を単騎で滅ぼし、名声を上げていった。
畏敬の念を込め、いつしか英雄と呼ばれるようになると――彼はいよいよ、サドネス公国君主が暗殺された事を機に、自ら君主の血統を次々と殺したうえで乗っ取ったらしい。
支配下にされていた帝国にすらも宣戦布告し、たった一人で元の帝国を滅ぼしたというのも、彼の実績によるものだ。
この後に、元サドネス公国首都だった領土を拡大させ、ブロード王国を敷いた。
国を滅ぼし、敵は無く百戦錬磨にして歴戦不敗。
何度でも言おう、彼はまさしく”異常”だった。
そんな彼が倒れたという、絶望に震えると同時に、僕の心は、何故か―――不思議なほどに高鳴っていた。
頭を抑えつつ、乱れた自分の思考を鑑みてみる。
揺らぐ脳内から、導き出された解は、どう思考してみてもひとえにたった一つ。
”彼を倒す程の力の持ち主”に対する興味だった。
戦争状態にあった、グラニオス帝国から奪ったという神話級の宝物――光聖竜の巻物を開放したことによる強力な光の魔術の数々。
持ち前の巨体と戦闘センス。
それらを総動員してもなお、この王を破った存在は、どれほど強いのか。
もはや、僕の脳髄は謎の存在に対する関心で埋め尽くされていた。
ふと我に返り、白衣のポケットから千天鏡を取り出す。
これを使い、王の死体に受けた負傷を分析するのだ。
千天鏡を通して、分析してみると驚くべきことが映し出された。
王の死体に付着していた、魔術の残り香は闇でも、光属性でもない未知の属性だった。
魔術は、行使しそれが相手に当たれば属性が残り香として付着する。
千天鏡は、それを色として視覚に映し出すものだが、今回ばかりは僕も、故障を疑わざるをえなかった。
体に付着していたのは闇の漆黒でも、光の純白でもない。
しかし、漆黒よりも黒く、純白よりも白い矛盾したそれは、色として認識するには脳に大きく負担をかけるような代物だった。
現に、千天鏡で覗き込んでいる僕には内側から鈍器で直接殴られたかのような鈍痛の症状が現れていた。
相反した色が、混ざり合いつつも元の色の特性を併せ持っており、色としてもこれは未知の色なのかもしれないと認識させられる。
頭痛や未知の色との遭遇、王の死という不快で衝撃的な事象が起こっているわけだが――更にそれらは愛おしいほどに僕の関心を引く。
生唾を飲み干し、僕は体勢を整えて小さなガレキを少しづつ退かしていき、王の体をガレキの山から引き上げた。
引き上げた王の体は、満身創痍に等しく、つい数時間前まで生きていたのが疑問なほどのありさまだった。
王の体を、千天鏡ごしによりじっくりと観察しようとすると。
「おい! 何をしている!!」
誰かから後ろから声をかけられた。
「なんですか、出合い頭に」
分析を妨害されたかのように思い、思わず振り返る僕の表情は歪められた。
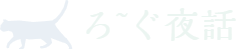


コメント