
僕の眼が覚めた時。
辺りは静寂に包まれていた。
多種多様に、様々な髪色と背丈の人々が皆祈りを捧げるかのように縮こまり、一瞬たりとも声を上げることなく。
ただ、屠殺を待ちわびる家畜の如く――民は虚ろな目をしばたたかせていた。
この世の、地獄の図だ。
(ここで誰かに話しかけるのは、流石に空気を読めていないか)
僕が壁に寄り添い、再び瞼を閉じようとした直後。
壁伝いに、戦いの衝撃が頬と耳に響いた。
肉が爆ぜる生々しくもおぞましい音と、抗う金属の弾ける音。
嫌悪すべき残響が、僕の顔に容赦なく降り注ぐ。
残響は、段々と激しくなっていき――それに伴い空洞内を揺らしていった。
尤も、空洞の中の人々は、ただ震えるばかりで変わりはなかったのだが。
各々が身に着けた、ロザリオを握りしめ始めている事を除いては。
ロザリオは、この地に眠ると云われている守護神にして”属性”の象徴である、竜の形を模している。
竜教の教徒たる証だが、信仰している対象は大陸によってまちまちとなっており、この大陸では――稲妻を司る竜”雷竜”を信仰しているという。
信仰との関連性があるかは存じないが、雷属性の魔術は、城下町の町民の得意とするところだった。
王もまた、その一人である。
それを示すかのように、上階から稲妻の発生する音が聞こえてきていた。
防衛戦を繰り広げていることは、明らかだろう。
稲妻の音が、途絶えると――更なる上階が崩落する音が空洞内を振動させる。
しばらくして、振動が終わる。
それは、共に――全てが終わった事を告げていた。
完全な静寂を合図に、出口の階段の奥から光が漏れ出していく。
僕は、それを見て出口の方へと向かっていった。
(終わったのか。今回の戦もきっと――)
階段に足を踏み入れ、両開きの扉を開ける。
目の前に広がるは、清々しいまでに―――荒涼とした城内。
倒壊した、上階の廊下だった残骸がそこらたしに落ちていた。
無数に散らばる、無残なるガレキの数々がそこで起こっていたであろう戦いの凄惨さを物語る。
ガレキの上には、やはりというべきか――夥しい血しぶきで染まる武器の破片が散らばっていた。
(相変わらず、酷い有様だな。さて、王はどこだ?)
宙を舞い続ける土煙を、白衣の裾で振り払い、あるいは口許へともっていきながら、僕は歩みを進めていった。
目指す先は、音の震源地。
即ち、”王の戦場”である。
僕が周囲を散策し、とうとう足が玉座へと繋がる階段だったであろうガレキの山へ着いた時。
足元の、ガレキに埋もれた長い腕が僕の歩みを阻んだ。
(? 誰の腕だ?)
階段を構成していた、石材とすら思えるほどに硬質で凹凸の出ているそれは、甲から鮮血を垂れ流していた。
腕の前でしゃがみ込んだ時――僕の背筋を悪寒が伝った。
赤く染まった皮手袋に包まれた、男の腕。
それを目視することは、絶望を意味していた。
額に流れるは、滝飛沫の如き粒々。
口から洩れだすは、嗚咽。
自然と、その亡骸の前で僕は体を震わせていた。
僕が連呼していたのは、たった一言の連続だった。
「ありえない」
と。
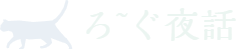


コメント